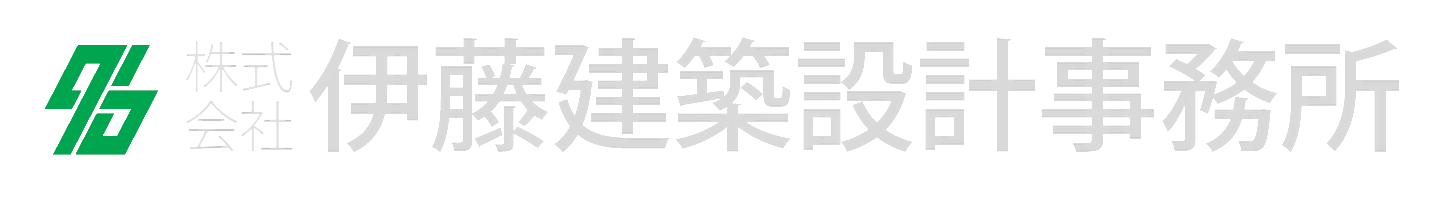先日岐阜県に行く用事があり、その時の帰り道に「イオンモール土岐」というショッピングモールに立ち寄りました。 見どころがいくつかありましたので、今回は 「イオンモール土岐」で見つけたこと、考えたこと などをシェアしたいと思います。 イオンモール土岐とは? 「イオンモール土岐」は2022年の10月にオープンした比較的新しい施設です。岐阜県の土岐市というところにあり、ここは「陶磁器の生産量が日本一」のまちとして知られています。 ■ モールへのアクセスと周辺情報 モールへのアクセスは東西に走る中央自動車道の土岐インターから車で10分、南北に走る東海環状自動車道の土岐南インターからは車で5分ほどで行くことができ、遠くから来る利用者もアクセスしやすい場所にあります。 モールの周辺には美濃焼ミュージアムや県立の陶芸美術館、また、車で15分ほど行ったところに多治見モザイクタイルミュージアムがあります。 ■ 建物の概要 敷地面積は約203,000㎡。建物の延床面積は約72,000㎡、S造の2階建てです。 敷地面積は全国のイオンモールのなかでもトップクラス、延床面積は中規模クラスのようです。先程紹介したトキニワはモールの東側にあります。 モールの周囲には駐車場が配置され、日帰り温泉や住宅展示場、ゴーカートのサーキット場、ガソリンスタンドなどが併設されています。 デザイン面での特徴 先に述べたように陶磁器が地域にとって身近な存在になっているので、イオンモール土岐も建物の外装や内装に土岐市内で生産されたレンガやタイルを使用しています。 建物正面の外壁部分に施されたタイル張りのアクセントウォールは、森や海を表現したパステルカラーとなっています。緑色のタイル部分を近くで見るとこのようになっており、かなり迫力があります。(画像1 ) 土岐市の特色を反映した外装として、 工事中に発生した掘削土を材料に使用し、地元のタイル工房とのコラボレーションで制作された唯一無二のタイルを使って、 森林に差し込むこもれびを表現しているそうです。 以下の画像は、2階のテラスにあるエントランス前です。 右手にレンガ張りが見えますが、このレンガは店内の柱型の仕上げなど内装にも使われていました。建物の中でもよく見かけたのでおそらく地元産のレンガだと思
スマホ・オーディオブック活用読書術
今回は スマホ・オーディオブック活用術と、試してわかったこと についてです。 スマホ・オーディオブック活用読書術 以前にテレビで、こんな読書術を紹介されている著名人がいらっしゃいました。 移動中等にスマホでオーディオブックを聞いて、気に入ったら本を購入する。 聞く速度も1.5倍速等で聞くとより多くの本が聞ける。 私は活字に他人より触れてきていないので、オーディオブックから始めればいいかなと思い、少し前からこの手法を始めました。 オーディオブックのメリット オーディオブックのメリットには以下が挙げられます。 隙間時間で読書が出来る ながら読書が出来る 読書ジャンルの幅を広げられる 倍速機能で速読が可能 等 オーディオブック取扱いアプリ比較 オーディオブックを取り扱っているアプリをいくつか調べてみました。 オーディブル Amazonのオーディオブックです。単品購入の他、月額の聴き放題もあります。 配信は40万作品以上で、聴き放題も12万作品以上です。 配信数が他より多いです。 オーディオブック オトバンクが運営してます。単品購入のほか聴き放題も出来ます。 聴き放題の配信が1万5千作品以上とオーディブルより少ないですがリーズナブルです。 ヒマラヤ 中国の巨大音声プラットフォームの日本サービスです。聴き放題の配信が1万作品以上とオーディブルより少ないですが料金はリーズナブルです。 私は個人的にAmazonをよく利用しているので、オーディブルにしました。 聞ける本は自己啓発からビジネス、健康から小説等様々な本があります。 おすすめ本の発見 オーディブルを試していく中で、面白い本がありました。 佐久の浅間病院の外科部長の尾形先生の「専門医が教える 肝臓から脂肪を落とす食事術」です。 3人の脂肪肝の患者さんが食生活を通して改善していく本です。 また、本の最後のオーディオブック特典のなかで、尾形先生自身のお話がありました。 以前に外科医にとって重大な片目にメスを入れ、目が見えなくなり不安に陥ったことがあったそうです。 その時にオーディオブックを知り、良く聴くようになり救われたとのこと。 自分が本を出版するときはオーディオブック用に執筆しようと思われたそうです。 &nbs
現行プロジェクトの一部ご紹介
今回は 今動いている現場で感じたこと をご紹介をしたいと思います。 白馬で動いているプロジェクトは冬場の工事ということで、雪のため、工期が当初の予定であった2月から3月に延長されました。 過去に手がけた道の駅に続く同じ道の駅関連ですので、1度監理をしたからスムーズにいくだろうと思っていましたが、やはり現場が変われば、施工者も変わり、考え方等も様々になってきます。意思の疎通等の観点も含め、どのように伝えればお互い気持ちよく仕事ができるか、毎回考えさせられます。 またこの現場で一番考えさせられたことは、やはり現場調査はしっかり行わないと実際に現場へ入って苦労するということでした。 今回は後から分かった排水経路関連の事情があったため、工事の増減の調整が必要となりました。 他の監理業務でもそうですが、増減が必要となれば、協議書を作成しなければならず、プラスアルファの仕事が発生します。もちろん仕事が落ち着いていれば、そういう事に充てる時間は十分とれますが、業務が集中している時期にはいろいろ追われてしまうことになります。 また、道の駅の公衆トイレの改修設計で感じたことは、「時代に沿った公衆便所となってきている」ということです。 他の現場でもそうでしたが、衛生器具の部品が膨大な量あります。 今回器具の搬入立会いをしましたが、ある程度小規模な公衆便所であっても大型トラック2台分の段ボール箱が搬入されました。 過去の似たような案件の搬入関係者の話では、 「色々なものがあると把握するのも大変ですし、想像以上にものすごい人工がかかる」とのことでした。 やはり機能や快適さを求めれば業務もそれなりになるのだと、現場監理を通して改めて実感している次第です。 本プロジェクトはまもなく終盤を迎えます。 引き続きしっかりと取り組んで参ります。
トルコ・シリア地震と建築物への影響
今日は2023年2月6日に発生した トルコ・シリア地震と建築物への影響 についてです。 トルコ・シリア地震の実体 日本時間午前10時過ぎに発生したトルコ・シリア地震の規模は、マグニチュード7.8。 そのエネルギーは、2016年の熊本地震の16倍、 阪神・淡路大震災を引き起こした地震の22 倍にのぼり、「世界最大規模の内陸地震」 と言われています。 地表の断層のずれ幅も大きく、 国土地理院が、 宇宙航空研究開発機構(JAXA ジャクサ)の地球観測衛星「だいち2 号」の観測データをもとに分析したところ、 地震による地殻変動はおよそ400キロに及び、阪神大震災の約4倍にあたり、2016年の熊本地震の10倍近く、最大約4メートルの横ずれが生じています。 米地質調査所によると、 最初の地震の規模はマグニチュード7.8、その約9時間後に7.5の余震が起きました。 日本の気象庁の震度に換算すると、 一部で最大の震度7相当の強い揺れが起きていたといいます。 2023年2月23日現在、 トルコ・シリア両国の死者数は計50,000人以上になりました。 世界保健機関(WHO) による推計では最大2,300万人が被災したと見られています。 被災地で避難生活を送る人は100万人以上とみられ、テント30万張りが設置されたほか、仮設住宅 10万戸も設けられるといいます。 建物の倒壊状況とトルコの耐震基準 この地震では、多くの建物が倒壊しました。 その中には、耐震性能をうたう比較的新しいものも含まれていました。 真新しいマンションが崩れた様子に、トルコ国内では怒りの声が上がっています。 全壊した建物の中には、新築の集合住宅も含まれているため、建物の建築基準について喫緊の深刻な懸念が上がっています。 そもそも、今のトルコの建築工法なら、今回のような揺れの強さに建物は耐えられるはずでした。 そして、過去の震災の経験から、トルコでは地震に備えた耐震基準が徹底されているはずでした。 (1999年に北西部イズミットで起きた地震では、1万7000人が死亡しています。 ) トルコでは2018年に発生した災害や、これまでの被災経験から、より厳しい安全基準が導入され、建築規制が強化されてきました。東京大学地震研究所の楠教授によれば[※1]、最新のトルコの耐震基準は日本と変わらない水準だということ