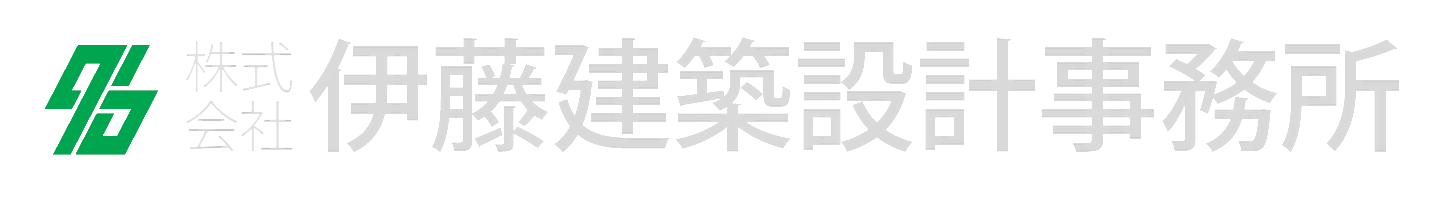今回は、長野県松本市で開催される松本建築芸術祭についてです。 2024年の今年は3回目の開催で、2月23日から3月24日まで行われています。(本ブログ掲載時では芸術祭は終了しています。) マツモト建築芸術祭とは マツモト建築芸術祭は、松本で90年以上の歴史を持つ扉温泉を擁する扉ホールディングス株式会社の齊藤忠政社長が実行委員長となり、呼びかけをされスタートした芸術祭です。2022年から続いています。 松本市の魅力のひとつであるノスタルジックな建築物を会場にアート作品を展示、その対比・融合・共鳴により、新たな化学変化を起こし、街の活性化につなげようという趣旨のイベントです。 松本市は近代名建築の宝庫 松本市には国宝「松本城」や「旧開智学校」だけではなく、なまこ壁の土蔵造りの建物や、正面 を西洋風に装飾した「看板建築」といわれる店舗兼住宅など、日本の近代化を象徴するさまざま な建築物が数多く残り、独特の街並みを形作っています。 この芸術祭では、普段の暮らしの中に存 在するそのような「名もなき建築」の価値を多くの人たちに再認識してもらい、活用に向けての 後押しをすることも目標としています。 また、観光客が少なくなる冬の時期に毎年開催し、街のにぎわい作りに寄与しています。 また、芸術祭をきっかけに古い建築物の活用と保存への意識も高まっています。松本の芸術文化振興や観光 の付加価値を高めることに加え、失われゆく〈名建築〉を生きた形で活用することや地域活性化への取 り組みにも力を入れるため、継続の開催を目指しています。 2024年度会場は旧松本市博物館 今年で第3回目を迎えるマツモト建築芸術祭2024 ANNEXでは、《消えゆく名建築 アートが住み着き記憶する》松本城に隣接する旧松本市立博物館をメイン会場として開催予定です。 同館の取り壊し前 に開催される最後のイベントとなります。 なお、こちらの旧博物館は現在弊社で解体の設計を請け負っています。 なお、新しい松本市博物館の設立にも、弊社が携わっています。 詳細は、こちら(実績ページ)をご覧ください。 旧松本市立博物館の歴史 旧博物館は、1906(明治39)年に創立された「松本紀念館」を前身としており、1967(昭和42)年、松本城二の丸に新築され「日本民俗資料館」として開館しました。 当時は北信
Geminiに聞く AIと建築構造設計
今回は、昨今話題のAIと建築設計業務の関係について考えます。 具体的にAIは設計において何ができるのかイメージしにくかったので、身近なAIであるGoogleのGeminiに質問しながら考察を深めます。 建築構造設計におけるAIの可能性 (Geminiの回答) Geminiに、AIは建築構造設計において何ができるの聞いてみました。以下4つのポイントに分けて回答してくれました。 設計支援 近年、AI技術の発展は目覚ましく、建築構造計算分野にも大きな影響を与えようとしています。従来の構造計算は、経験と勘に基づいて行われてきましたが、AIは膨大なデータを学習し、設計者の経験や勘を超える精度で構造計算を行うことができます。また、AIは、設計条件に基づいて最適な構造部材を提案してくれ、自動的に設計図を作成することができます。 安全性向上 AIは、人間が見落としがちな要素も考慮して設計を行うことができます。例えば、地震や台風などの荷重だけでなく、温度変化や風圧などの影響も考慮することができます。 コスト削減 AIは、設計作業を自動化することで、設計時間を大幅に短縮することができます。 AIは、構造解析結果に基づいて、材料の使用量を最適化することができます。 AIは、施工計画を最適化することで、施工の効率化を図ることができます。 その他 AIは、従来の構造形式では実現できなかったような、新しい構造形式を開発することができます。 AIによる建築構造設計の課題 (Geminiの回答) AIによる建築構造設計は多くの可能性を秘めている一方で、いくつかの課題も存在します。 課題について質問したところ、回答は以下の通りでした。 責任の所在:AIによる設計ミスが発生した場合、誰が責任を負うのかが明確ではありません。設計者、AI開発者、建築主など、誰が責任を負うべきなのかについて議論されています。 倫理的な問題:AIが設計した建築物が、安全性や美しさなどの観点から問題ないのかが議論されています。AIは人間の価値観や倫理観を理解することができないため、安全性や美しさなどの観点から問題のある建築物を設計する可能性があります。 AIによる建築構造設計の実例 ここでAIが実際に業界内でどのように実用されているのかについても聞いてみました。スーパー
令和6年実施 労務単価引き上げと働き方改革
今回は、令和6年(2024年)から新しく実施される公共工事設計労務単価の引き上げと、働き方改革について掘り下げていきます。 公共工事設計労務単価とは何か? 公共工事設計労務単価とは、公共工事の工事費の見積もりに使われている単価で、工事現場で働く人に支払われる賃金の基準となる値です。 内訳は以下の図の通りです。 都道府県別、職種別に定められた単価の値は、国土交通省のホームページで確認できます。 【参考】国土交通省ホームページ :https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001724088.pdf これは毎年見直しが行われます。 価格の変動としては、平成25年(2013年)以降、12年連続で毎年上昇しています。 今回の変更では何がどう変わるのか? 令和6年(2024年) 3月から適用される公共工事設計労務単価が、同年2月16日、国土交通省から発表されました。 全職種において、引き上げがあったことが、以下の図表から見受けられます。 つまり、労働者一人に対して事業者が支払うべき金額が上がります。 全職種での単価の平均は23,600円となり、前年比で5.9%増加します。 これは、建設業界で時間外労働の規制が強化されるのに伴って、人手不足や待遇改善が課題となることを見越しての措置です。 ちなみに、昨年も前年比5.2%と大きく引き上がりましたが、今回はさらに上昇しています。 国土交通省の発表内容ポイント 今回国土交通省から発表された内容のポイントは以下の通りです。 全国全職種の単純平均は、前年度比で5.9%引き上げ これにより平成25年の改定から12年連続引き上げに →平成25年には、必要な法定福利費(※) 相当額を加算するなどの措置が行われ、大きな変化があった ※法定福利費とは、従業員を雇っている事業者に負担が義務付けられている保険料などのこと。 労務単価には 事業主が負担すべき人件費(必要経費)は含まれていない。 “労務単価が23,600円(100%)の場合には、 事業主が労働者一人の雇用に必要な経費は、33,276円(141%)” ※以下の図 参照 今年2024年から罰則付きの時間外労働規制が適用される 他にも今年度の変化として特筆すべきは、201
人生の三つの坂と設計業務
一般的によく言われている、人生の中にある「三つの坂」を、皆さんはご存知ですか? 一つ目の坂は「上り坂」、二つ目の坂は「下り坂」、三つ目の坂は「まさか」です。 この話についてもう少し掘り下げ、筆者の自分なりの考察を加えてみたいと思います。 一つ目の坂「上り坂」 まず一つ目の「上り坂」ですが、これは気分がいい時、調子がいい時、仕事がはかどって順調に進んでいる時などのことです。よく「右肩上がりだね」とか「破竹の勢いだね」とか、言われる時の状態です。 どちらかというと良いイメージが大きいのが「上り坂」ではないでしょうか。 坂を登っている最中は汗もかくし苦しいし疲れますが、その先に目指すべき目標やゴールがあり、それを掴めたときの喜びが大きいですので、途中の労力や疲れは忘れてしまうこともあるでしょう。 二つ目の坂「下り坂」 次に二つ目の「下り坂」です。こちらは、転がり落ちる、楽に進める、何もしなければ自然と下に向かうというイメージがあり、気分が落ち込んでいる時、会社の業績が悪い時などのことを言います。 どちらかというと悪いイメージが強いのが「下り坂」ではないでしょうか。 三つ目の坂「まさか」と対策 そして三つめの坂、「まさか」です。 いつ・どこで・どのように起こるかわからない出来事に遭遇して「まさか…!!」となる時のことですね。 日々の生活における小さな「まさか」から(髪を切りすぎてしまったとか、仕事を一所懸命やったのにこんなはずじゃなかったとか、予定に間に合うように家を出たけど渋滞にはまって遅れたとか…) 想像もつかない大規模な「まさか」まで(世界各国での紛争・戦争勃発や、風水害・火災・能登半島地震などの天災など)いろいろあると思います。 ここまでの三つの坂は、いずれも平坦な道ではなく坂道なので、どう乗り越えていくかが課題であると考えます。 設計業務内での三つの坂 ここまでの坂の話を設計の業務に置き換えて考えてみます。 設計業務内での上り坂 「上り坂」の時というのは設計時に次から次へと良いアイデアが浮かび、クライアントが望んでいる理想の建物に形づくられる絵が見える過程ではないかと思います。 一つ一つの要件をクリアするのは大変ですが、そこには大変なやりがいがあります。 クライアントの要望とこちら