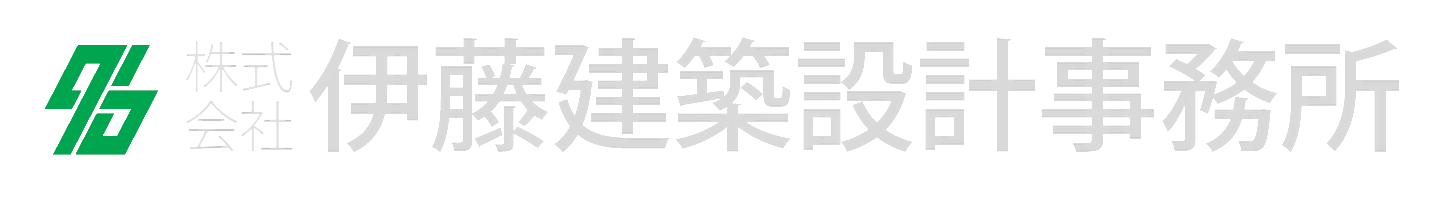だるまの目は、「左」と「右」のどちらから目入れしますか? いざ、目を入れるときに、左目なのか右目なのか悩むときがあります。 今週のスピーチは、だるまの目入れの話を聞きました。 目の入れ方は、願掛けをする際に、始めにだるまの左目に目を入れます。 そして、願いか叶ったら右目に入れます。 その理由は、諸説あるそうですが、物事は東で生まれて西で無くなると言われていることから、 だるまを南に向けたとき、東になる左目から目を入れ、 西になる右目という順序になったと言われているそうです。 その他の理由に、太陽が東から西に動くとこから、だるまを南に向けたとき、 東になるだるまの左目から目を入れるという説もあります。 しかし、必ずだるまの左目から入れる決まりはなく、選挙の時は立候補したら右目に目を入れ、 当選したら左目に目を入れることが多いようです。
言葉の由来
気温の低い日が増え、秋らしくなりましたね。 紅葉や秋の収穫など、秋を楽しまれている方も多いかと思います。 先日のスピーチは、食材の名前の由来やそのほかスタッフが気になる言葉の由来について聞きました。 サーロインステーキの語源は、英国王がこのステーキを出された際、あまりの美味しさに 「この肉にサー(ナイト爵)の称号を与える」と言ったことから、 「サー(ナイト爵)」の「ロイン(腰肉)」で「サーロイン」になったという話があるそうです。 アイロンの由来は、伝来した当時、厚い鉄でできた舟形の枠に中に熾(おき)を入れて加熱していました。 それを初めて見た日本人が「それは何ですか」とアメリカ人に聞いたところ、 厚い鉄でできた舟形の枠ではなく、その材質を聞かれたと思い「アイアン(鉄)」と答えた為、 「アイアン」が「アイロン」になってしまったようです。 普段何気なく使っているたくさんの言葉。 それぞれにルーツがあります。 気になった言葉の由来を調べてみると、なるほどねっと思う言葉や、 その言葉からは思いもよらなかったのものに行き当たることがあります。 とても興味深い話でした。