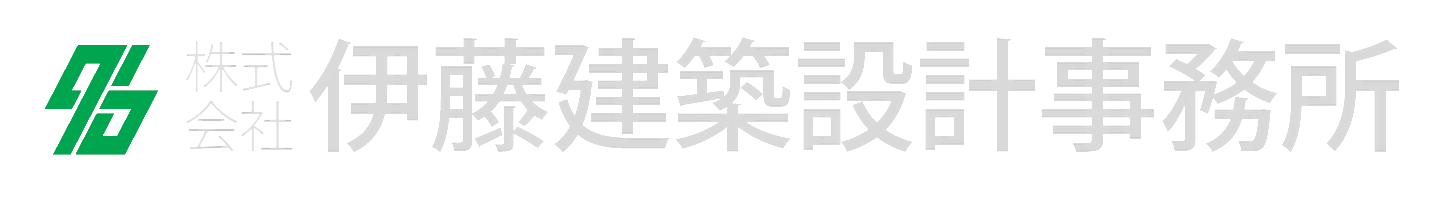今回は、耐震改修における工事中の問題、 特に居住者目線での問題について、実際の現場ではどんな問題が起こりうるのかをシェアしていきます。 これまで伊藤建築設計事務所で請負った耐震改修の一例 建物内部の壁の補強 建物外部への補強材の設置、交換 梁、柱の設置 トグル制震ブレーズの設置 耐震改修のリクエストの傾向 予算的な問題から、「建て替えは難しいので耐震改修を」となるケースが多いです。 耐震改修方法は数多くあるので、発注者様の要望を聞いて選定していきますが、 室内を狭くしたくない 外部の意匠を損ねたくない 居ながら改修を行いたい など、さまざまなタイプのリクエストがあります。 その中でも、 「(居住者の方が) 建物の中に居ながら、改修作業を行なってほしい。改修作業中も建物の中にいたい」 という希望は、ほとんどの方が持たれます。 やはり工事中に移動する場所を確保するのは大変ですし、仮にそういう場所があったとしても、移動場所の改修費・移転費など多くの費用がプラスアルファでかかってしまうためです。 低騒音工法の実際 先に触れた要望が多いこともあり、全ての耐震改修工法は、 「(居住者の方が)建物の中に居ながら、改修作業ができます」「低騒音工法です」と、うたわれています。 ただ一言に低騒音工法だと言っても、メーカーや監理者レベルでは、居住者目線でのを感じ方をうまくとらえられていないことが多いにあります。 それなりの騒音が出てしまうことは工事開始前に分かっていますので、事前説明をさせていただいていますが、 実際に工事が始まると、予想より酷かったという理由で、施工者である私たちが全ての工法で呼び出され、対応を行うことも起こります。 実際の騒音や振動を確認する際、施工の技術者レベルでは、そこまでの問題ではないと判断されるケースでも、居住者の目線で言えば、1日中その騒音・振動にさらされているわけですから(一方技術者は30分のような短い時間だけその場に行って確認をし、その後帰ってしまうのが普通ですから)、一般的に予想されるより実際はデリケートな問題です。 改修中の騒音問題の解決法 工期に余裕があれば、特に騒音が想定される、はつり・アンカー工事などを就業時間後や休日工事とすることも出来ますが、そうすると今度は周辺住民の迷惑になってしまうなど、検討項
企画展とウィリアム・モリスの魅力
今回の記事では2023年4月15日から6月4日にかけて、長野県・松本市美術館で開催中の企画展「アーツ・アンド・クラフツとデザイン -ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで-」に行ってきたレポートをお伝えします。 なお今回は、書き手である私が特に興味のある「ウィリアム・モリス」に焦点を当てその魅力に迫る形で、企画展示で見てきた内容、モリスの魅力についてご紹介していきます。 松本市美術館の企画展示を見に行ってきました。 今回の企画展は「アーツ・アンド・クラフツとデザイン -ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで-」というタイトルです。 19世紀に活躍したイギリス人芸術家で「モダン・デザインの父」モリスが主張した、生活と芸術の融合、そしてその思想に共鳴したデザイナーや建築家により発展した「アーツアンドクラフツ」をめぐる展示でした。 今回の展示会では、モリスのテキスタルデザインによる版押しの壁紙やカーテン、タペストリーといったファブリックの本物が間近に見られるということで、またとない機会を逃すわけにはいくまいと美術館まで足を運びました。 ウィリアム・モリスという人物 1834年イギリスで生まれたウィリアム・モリス(William Morris)は、若いころに父親を亡くし、苦学の末に大学で建築を学びました。一度は建築事務所で働くものの、その後、絵画に移行し家具の絵付けや内外装を手掛け、友人らとのちのモリス商会を立ち上げています。 産業革命で粗製乱造される工業製品が身近に溢れていくのを憂い、手仕事にこだわったテキスタイルや家具、日用品などを制作し、普及にも努めました。彼のこの動きはのちのアーツ・アンド・クラフツ運動の先駆けでもあります。 この記事の著者である私は、昔からモリスファンで、モリスにえもいわれぬ親近感を抱いています。 ということで、今回美術館では、4部構成の展示のうち、モリスを取り上げた前半部分をメインに見てきました。 モリスの作品 彼の手仕事の中で関心させられるのは、例えば、大ぶりな柄の多色刷りの壁紙でも、ムラや継ぎ目が全く目立たず、仕事ぶりが繊細で正確であるということです。 まさにクラフトマンシップを
電気と建物の基礎知識
今日は、私たちの身近にある、電気と建物の仕組みのお話です。 アースって何? まずは今回の最初のキーワードである「アース」について見ていきましょう。 一般的に「アース」と呼ばれるものは、「接地」のことを指しています。 アース(英語:earth)は言葉の通り地球を表し、地面と接触状態になっていることを意味します。 また、地面(地球、earth)とつながっている装置を意味する場合もあります。 「接地抵抗」は、電気機器の本体と地面の間の抵抗値(電位差)のことを指し、地面へどれくらい電流を流せる状態であるのかという目安のことを指します。 身の回りのアース 20m以上の建物には、避雷設備を設備することになっていますが、これには地面へと異常電流を流す設備が接続されています。 また、電気機器周りや家庭の洗濯機、冷蔵等の水回りにもアース線が設置してありますので、この仕組みは皆さんもすでにご存じかもしれません。 落雷や漏電が発生した場合、身体の安全を守ったり、機器を損傷から守ったりしてくれますので、必要不可欠な設備と言えるでしょう。 アースにまつわる取り決め 以上に例を挙げた電気を地面に流す仕組み「アース」は、電気の基本的な設備であり、重要な設備でもあります。 これに関しては、建築基準法や電気事業法、労働安全衛生法などによって法的な取り決めがされています。 当然、接地抵抗には法律で定められた「規定値」があるわけで、この規定値の範囲であればアースは正常に機能し、安全な状態であると言えます。 逆にこの規定値が取れていないと、電気が正常に流れてくれないことになるため、非常に危険な状態であると言えます。 建築の現場ではどんな問題が起きるのか ここでは以前実際に現場で起こった、接地抵抗に関する課題の例を紹介します。 一般的に山間地帯、川沿いでは、接地抵抗が取れない場合が多いので、十分な事前調査が必要です。 事前の地盤調査の結果は、建物の構造を考える上で必須のものですが、一連の電気関連設備を考える上でも必要なものです。 この案件では、設計の段階から事前に専門業者に依頼して、接地抵抗が取得出来るかどうかの調査を行っていましたが、当初より規定の接地抵抗を取ることが困難であることが分かっていました。 そこで考案した解決法は、裸銅線を約2km地中に