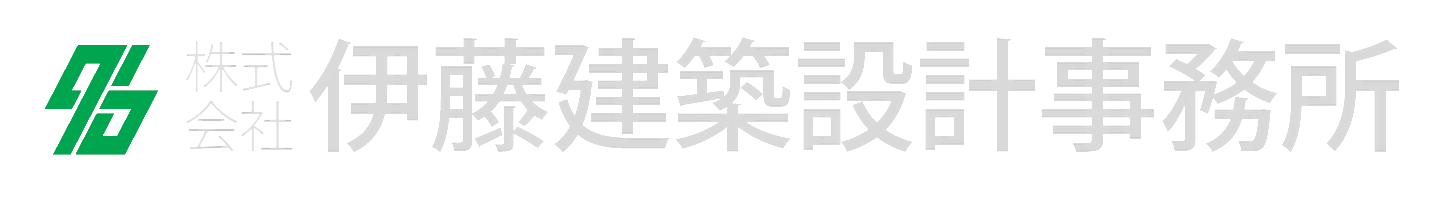今日は 住宅、非住宅についての最近の価格の推移を見て、その後、今後の私の予測をお話していきます。 データは新聞等で独自に調べたものを参照しています。 住宅価格の推移 現状分析 まず住宅について。 現在2023年6月時点で、国内の集成材が2023年4月時点に比べ1割ほど安くなっています。 (※集成材とは、複数の板を結合させた人工の木材のことです。) 2021年から、アメリカでの需要の高まりやコロナ禍のバランス崩壊などが原因でウッド ショックが始まり、集成材の値段も大幅に上昇しました。そして2022年の1月にはウクライナ戦争が始まり、値段は上昇したまま横ばいとなります。 この時点で、日本の住宅の着工数自体は減っていなかったのですが、商社が急いで集成材の原材料(ラミナ)を買い漁ったという背景があります。 この段階では特にカナダ、オーストラリア産のものの買い占めが起こりました。 価格に関してはこのまましばらく横ばいだったものの、2022年7月くらいから、また状況が変わり始めます。 今度は価格が異常な下がり方をし、1ヶ月にだいたい10%近くも下落し続けたのです。 これは慌てて入れた材料を放出したために、集成材の価格が一気に下がったという状態です。 製造コスト、人件費の上昇などがありましたが、それがあったとしても実際の集成材自体は安くなってきているという現状があります。 なお、国産材については、若干の下がりはあるのですが、これは集成材ほどの減少はないという状態です。 今後の推移予測 この記事の筆者の今後の予測ですが、ヨーロッパの方面から仕入れてる集成材原材料(ラミナ)の値段がまた最近上がり始めた現状を見ると、今後また集成材の価格が上昇し始めるのではないかと考えています。 非住宅価格の推移 現状分析 次に非住宅について。 2023年2月から3月頃、電炉大手の東京製鉄で、鋼材価格の引き上げが2%ほどありました。 そして現状2023年5月から6月は、価格を据え置き、つまりそのまま変化はさせないという状態になっています。 鋼材関係の最近の価格変動からの据え置きの裏には、中国の影響があり、中国からの安価な鋼材の流入が原因と言われています。 中国の経済状況、特に不動産関係について触れておくと、今中国国内での需要が減少しており、中国内で消費できない分が日本にも
アーツアンドクラフツ運動と民芸運動
こんにちは。今回の記事は、前々回のブログ記事「美術館企画展レポートとウィリアム・モリスの魅力」の続編です。 前々回の記事に影響を受けて、私(別のブログ担当者です)も美術館に足を運びましたので、そこで考えたことを記載していきます。 ※前回のブログをまだ読んでいない方はこちらから この記事では、ウィリアム・モリスが提唱した「アーツ・アンド・クラフト運動」と、大正から昭和初期に活躍した思想家・柳宗悦によって提唱された「民芸運動」の比較考察を行なっていきます。 二つの理論の違いを、わかりやすい言葉で明らかにしていきたいと思います。 「アーツ・アンド・クラフツ運動」とは何か アーツ・アンド・クラフツ運動とは、簡単にまとめるならば、 ウィリアムモリスのよって先導され、イギリスの産業革命による工業化によって失われた手工芸の復興を目指す民芸運動といえるでしょう。 もう少し噛み砕くと、職人による製作活動と労働の在り方についての問題提唱と理想の提示、ということが言えます。 ではここで、モリスの著書『民衆の芸術』の一文をご紹介します。 私の理解する真の芸術とは、人間が労働に対する喜びを表現することである。その幸福を表現しなくては、人間は労働において幸福であるとは言えないと思う。特に自分の得意とする仕事をしているときには、この感が甚だしい。このことは自然の最も親切な贈物である。 これは、あくまでこの記事の筆者である私の解釈ですが、 モリスは「労働と芸術は決して切り離されることのない隣り合ったものだ」と考えていたのでしょう。 労働があるのならばそこには自然と芸術が生まれるべきであり、それは自然からの親切な贈物だと表現しています。 「アーツ・アンド・クラフツ運動」は、 便利が強調された産業革命において、労働から生まれるべき芸術が生まれず、生活の豊かさが廃れていってしまうことを危惧して始まった運動であったとも言えます。 「民芸運動」とは何か それでは「民芸運動」とは何か見ていきましょう。 「民芸運動」とは、思想家の柳 宗悦 (やなぎ むねよし、名前はしばしば「そうえつ」とも読まれ、欧文においても「Soetsu」と表記される) によって先導され、日本で起こった「日常の暮らしに宿る美しさを追究」する運動です。 彼は、新しい機械や技術で作られた