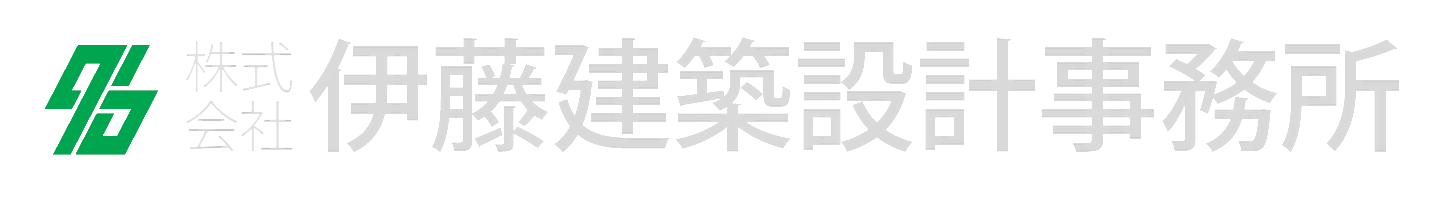「ファンを魅了する愛されるブランド」の調査結果 まず、最初に以下の表を見てください。 この表は「ファンを魅了する愛されるブランド」いわゆるファン度をパーセンテージで表したものです。(2022年4~5月、ファン総合研究所が実施) インターネット上でアンケートを行い、その中で「このブランドが好きか」や「これからもずっと応援していきたいか」などの設問から、どのくらいの割合の人が該当ブランドのファンなのかを算出しています。 この調査では、対象を7業界47ブランドとしています。 7業界の内訳は、ビール業界、お菓子業界、清涼飲料業界、ファーストフード業界、家電業界、化粧品業界、コンビニエンスストア業界です。 まとめると、この表では、調査の中でコアファンとファンの割合がトップだった企業を列挙しています。 ※一番右の列の【 】内の数字は業界平均のパーセンテージです。 調査の中では以下の4項目に関する質問を中心にアンケートを実施しています。 利用頻度 利用金額 NPS(顧客満足度) ブランドに対する価値や意向 また、別の指標として、 機能価値 情緒価値 未来価値(社会・未来に対するポジティブなイメージ) 上記の価値を図る指標も設けたそうです。 それでは以上の表の結果について、調査中にあったコメントや、ファンが支持する理由等を詳しく見ていきましょう。 主力商品がそのままコーポレートイメージになった例 アサヒビール ビール業界1位はアサヒビール。コアファンとファンの割合が32.1%でした。(業界平均は27.7%) 回答者からは「自分の生きがい」「これ以上至福を感じる飲み物は他にはない」といった高評価が寄せられたそうです。 同社はビールだけでも複数ブランドを展開していますが、「日本のビールといえばアサヒスーパードライ」という回答があったことからもわかるように、不動の主力商品がそのままコーポレートイメージにつながっているようです。 「あなたにとってのアサヒビールの存在は?」という質問に対し、 「相棒」「人生の伴侶」など単なる消費財を超えた、身近で深い関係を築いていることがうかがえます。「また父が大好きだった。晩酌はいつもこれだった」と親の影響を受けているファンの声もありました。 「昔から変わらない」が「安心」のイメージにつながった例 ブルボン 菓子
繰り返しの手法の面白さ
皆さんは、とある形の屋根やパーツが何度も繰り返されている様式の建築をご覧になったことがありますか? 繰り返しの技法を使うことで、建物に独特な個性が生まれます。 今回は、筆者である私が好きな、建築における「繰り返し」の手法のついて、その面白さを解説していきます。 「繰り返し」の手法が使われている建物コレクション 東京の銀座線渋谷駅の新しい駅舎 写真は、こちら (東京メトロのウェブサイト)を参照ください。 波形の形状が繰り返され、目を引く印象的なデザインです。 駅の機能上、駅舎は建物を長く作る必要があるので、必然的に同じ形状のものが何度も繰り返されることが多いです。 長野県の安曇野ちひろ美術館 写真は、こちら (美術館ウェブサイト)をご参照ください。 建物の屋根に繰り返しの技法が使われています。 「切妻屋根」の形式をとっていますが、もしこれが一つしかなかったら、無機質な屋根の倉庫のように見えてしまうでしょう。それが5つほど繰り返し同じ形の屋根を連続して繰り返すことによって、全体として見たときに面白みのある風景として出来上がっています。 繰り返し屋根が、周りの景色とよく溶け込んでいるところも美しさのポイントです。 街並みの中での「繰り返し」 商業施設・ミナカ小田原 こちらは最近できた商業施設で、蔵城の建物がいくつも繰り返されており、和風の美しい景色を作り出しています。大きなビルの前面に小さな和風の蔵を繰り返すという点においてもユニークなつくりです。 写真は、こちら(ミナカ小田原ウェブサイト)をご参照ください。 海外の例・イタリア ヴェネツィアのブラーノ島では、建物の外観はよく似たものが連続しているが色がカラフル、という事例もあります。 スタイルが統一されているので色々な色がありカラフルであっても、どことなく統一感のある街並みです。 残念ながらこのタイプは日本では受け入れられないでしょうが、事例としては面白いですね。 海外の例・ギリシャの外観の統一 こちらギリシャのサントリーニ島では、白という「色」で繰り返しがなされています。 同じ色の建物が連続し、その連続により街並みが完成しているので、統一感があって大変美しいですね。 他の国でも、ヨーロッパは屋根瓦の色が同じという例も多々見られます。 こういった色の