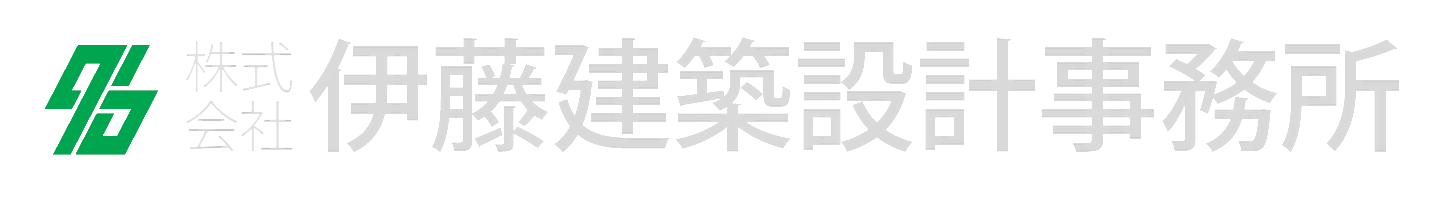この記事では、マンションの既製コンクリート杭などに採用されるハイブリッドニーディング工法とはなにか、解説していきます。また弊社での取り扱い事例も一部ご紹介します。 建築現場で使用される杭の施工法を種類別に紹介 施工方法で大まかに2種類に分類できる 杭工事は施工方法で分類すると、 ・既製杭工法 ・現場打ちコンクリート杭工法 に分けられます。 図から分かるように、既製杭工法では、別の工場で作られた電信柱のようなコンクリート柱を杭として埋め込む方法です。一方で現場打ち杭工法は、あらかじめ開けた穴に鉄筋で組んだカゴのようなものを入れ、そこにコンクリートを流し込むという方法です。 また、上の図から分かるように、既製コンクリート杭の中には3種類の杭工法があります。 その3種類とは 打ち込み杭工法 埋め込み杭工法 回転杭工法 です。 それぞれの杭の特徴 打込み杭:支持力は大きいが、施工時に振動や騒音がある。このデメリットのため、最近はあまり採用されない傾向がある。 埋め込み杭:支持力については、打ち込み杭よりは支持力は小さいが、現場打ち杭よりは大きい。振動や騒音も打ち込み杭に比べると小さい。さまざまな工法の中でも、いろいろな要素が中間的である工法。 回転杭:先端に羽根を取り付けた鋼管杭に回転力を付与し、地盤に貫入させる工法。 無騒音・無振動で施工できるが、地盤がに硬い石や異物が多く入っている場合、回転羽が破損する可能性がある。 なお、今回テーマとして取り上げたハイブリッドニーディング工法は、既製杭工法で、埋め込み杭です。 言葉の意味 ハイブリッドニーディングというとなかなか聞きなれない言葉ですが、 「ハイブリッド」は、異なる2つの要素、方式が組み合わさったもの、またはそのような性質を持つものを指し、「ニーディング」は英語で、こねたり練ったりすることを指します。 言葉の意味を見ることで、この方法のイメージが掴みやすくなったのではないでしょうか。 ハイブリッドニーディング工法とは ハイブリッドニーディング工法の概要 ハイブリッドニーディング工法はその言葉の意味からも分かるように、種類の違う杭を繋げて使用する工法です。 基本的に下杭には、節杭、または拡頭節杭、あるいは頭部厚型節付き杭など
デジタルスタンプラリーとは
デジタルスタンプラリーとは、従来のスタンプラリーを現代式にしたスタンプラリーで、スマートフォンやタブレットを使ってスタンプを取得できるタイプのスタンプラリーです。 今回は、最近地域活性化のため各所で盛んに行われているデジタルスタンプラリーについてまとめてみました。(※本記事は2023年現在の情報です) 長野県で見かけた身近な例 先日見かけたのは、こちらのデジタルスタンプラリーです。 ジャパンエコトラック八ヶ岳・諏訪湖 デジタルスタンプラリー2023 (https://www.japanecotrack.net/special/10) 松本駅のコンコースで、ポスターを見かけて存在を知りました。 このスタンプラリーの特徴は、公式アプリを使用することでデジタル式のスタンプラリーに参加できるということ。「ジャパンエコトラック八ヶ岳・諏訪湖」に登録されたルートを通過すると、自動的にデジタルスタンプが獲得でき、ルートを完走した際には完走の証であるデジタルバッジが獲得できるそうです。 また、完走してデジタルバッジを獲得して、アンケートに答えると、プレゼント抽選にも応募できるという特典があります。 他にもJR東日本主催で、人気アニメとコラボしたデジタルスタンプラリーを最近見かけました。 JR東日本 クレヨンしんちゃんスタンプラリー 参考URL: https://www.jreast.co.jp/crayonrally2023/ スタンプラリーはもう古い?!スマートフォン使用のデジタルラリーが普及 先の例に限らず最近では、スタンプラリーといえば、スマートフォンを利用したデジタルスタンプラリーの方が一般的になってきているようです。これにより、もう紙の台紙を持ち歩く必要はなくなります。 デジタルラリーの基本的な使い方 デジタルラリーの参加には、スマートフォンやモバイル端末の使用が必須です。 専用のアプリをインストールする、あるいは該当のWebページに行くことで、参加できます。 デジタルラリーに参加したら、その後は指定のルートの中のチェックポイントに実際に行きデジタルスタンプを取得します。ルート内にあるすべてのスタンプを集めて完走すると、プレゼントの抽選に応募することができます。 デジタルラリーの参加方法と使い方は基本的にどの企画もほぼ同じです。
京都・西本願寺訪問レポート
2023年の4月に、本ブログ記事筆者が個人的に京都の西本願寺を訪問しました。 今回は「慶賛法要(きょうさんほうよう)」という法要に参列したり、お寺の修復や瓦の様子について見る機会があったりしたので、そのレポートをお届けします。 はじめに 私が瓦に興味を持っている訳 この記事の筆者である私の親族には鬼瓦職人がおり、幼い頃より瓦に親しみがあります。必然的に瓦に注目することが多くなっていますが悪しからず。 西本願寺の概要 西本願寺(にしほんがんじ)は、京都にある浄土真宗本願寺派の本山の寺院で、正式名称は龍谷山 本願寺と言います。 境内には国の国宝、重要文化財などが数多く存在しており、西本願寺自体も「古都京都の文化財」としてユネスコより世界文化遺産に登録されています。 慶賛法要(きょうさんほうよう) 慶賛法要(きょうさんほうよう)とは? 今回2023年4月に私が参列した「慶賛法要」は親鸞聖人御誕生と立教開宗を慶び讃える御仏事です。 今年は親鸞聖人御誕生850年、立教改修800年という節目の年のお祝いでした。 慶賛法要(きょうさんほうよう)の様子 慶賛法要は西本願寺の御影堂(ごえいどう)で行われました。御影堂は、西本願寺の中でも国宝に指定されている建物の一つです。 以下の写真が御影堂です。 御影堂の中には椅子が数百並んでおり、全国から来た参加者に見えるよう、大型モニターが何台も養生された柱に設置されていました。 法要の中には本格的な雅楽も含まれており、貴重な体験でした。 西本願寺で見学した建築物、屋根と鬼瓦 法要の前後で、西本願寺を見学しました。 大玄関門の鬼瓦です。 ちなみに法要を行った御影堂(ごえいどう)や、寺院で良く見られる鬼瓦についてよく知らなかったので、帰ってから調べてみました。鬼瓦の代わりの獅子口(ししぐち)というそうです。(以下の写真参照) 上に「経の巻」という巴瓦を3つつけています。 御影堂の屋根の建築的解説 以下は御影堂(ごえいどう)の屋根です。 青字・青枠線部分の棟ですが、下から軒先の巴瓦を使った「甍 (いらか)」、「割熨斗瓦(わりのしがわら)」が何重もあり、最上部に冠瓦があります。 赤字・赤枠線部分は、獅子口(ししぐち)の下、妻側が蓑甲(みのこう)です。 その横の緑の部分は降棟(くだりむね)と言い