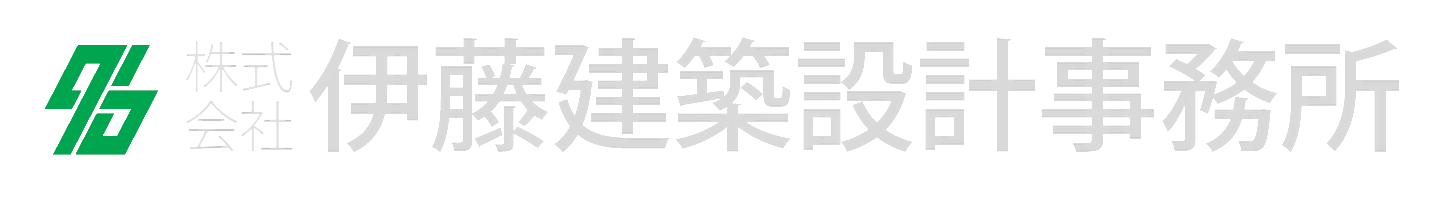先日、休みを利用して福島県へ旅行に行ってきました。 その旅行レポートを建築的な側面にスポットを当てながらお話ししていきます。 会津若松のさざえ堂 集合は郡山駅。松本からは片道4時間ほどで、なかなか遠い道のりでした。 郡山で集合後、会津若松に向かいました。 さざえ堂や白虎隊の石碑などを見て、戊辰(ぼしん)戦争に思いを馳せました。 左の写真の階段を登ったところにさざえ堂があります。 さざえ堂は二重構造のらせん階段を持ち、お堂としては珍しい建築様式を採用しており、国の重要文化財に指定されています。 さざえ堂はもともと三十三観音が安置され巡礼を行える場所でしたが、今では観音様はおらず13の偉人が奉られています。 新宮熊野神社 そこから北に向かい、新宮熊野神社へ向かいます。 目当ては熊野神社の拝殿にあたる「長床 (ながとこ)」という建築物です。 この長床という施設は熊野系の神社に多く見られ、拝殿としてだけでなく、修行僧の修行の場や、旅人の宿として利用されていたようです。 今回訪れた長床は、平安時代の寝殿造りの建築物であり、直径1尺5寸の円柱44本を5列並べて構成されています。 まさに「繰り返しの美学 ※」を感じるとともに、1尺5寸の柱の重厚さ、がらんどうであることで拝殿、修行、宿泊宿などの複雑な機能を受け入れられるフレキシブルな空間は、現代建築にも参照できるところが多いと感じました。 ※繰り返しの美学、繰り返しの手法の面白さについては以前こちらの記事でも取り上げています。 はじまりの美術館 猪苗代湖近くの宿で一泊して二日目、少し時間があったので小さな美術館に立ち寄りました。 その名も「はじまりの美術館」です。 この美術館は障がい者支援を行う社会福祉法人が、東日本大震災後の復興の一環として築100年以上の酒蔵をリノベーションして建てられました。その酒蔵は「十八間蔵」と称される通り桁行十八間ある蔵で、既存当時は一本ものの梁があったとのことでした。今は2本の梁を継いでいますが、それでも独特な空間を感じることができます。 内部も殴り仕上げの無垢フローリングや、小端立ての床材など、思わず裸足で歩いてみたくなるような楽しく気持ちの良い場所でした。 マテリアル重視で、建物全体がアート空間であるかのように感じました。 展示内容は現
林業プログラム「kikori塾」について
今日は、私が参加している「kikori塾」という林業プログラムについてのお話です。 kikori塾はどんなプログラムか プログラムは、1回のプログラムで2日間、全部で三回行われます。 ※現在この記事を執筆している時点では2回目を終えており、残すところあと一回です。 このプログラムは、南アルプスの景観が広がる伊那市で行われています。 伊那市の協力のもと、民間の林業従事者であるきこりから、山仕事や、木の植生を学びます。 実際に山に入り、間伐材をチェンソーで使って切り倒し、枝払いを行い、山から運びだします。その後、薪や合板、加工品として商品となる過程をお手伝いしながら、山暮らしを体験していきます。 参考外部サイト: https://smout.jp/plans/11703 なぜ参加したのか このプログラムに参加するきっかけは、SNSの広告でした。ちょうどその頃、再生可能エネルギー、ゼロカーボン、といったキーワードについて、いち個人単位で、どんな活動が出来るのだろうかと考えていました。 また、林業の実態はどんなものだろうかと興味を持っていたことも理由です。林業の抱える課題は「担い手となる人材不足」「森が荒れ放題であること」などといったことを良く耳にしていましたが、リアルな現状を知りたいという思いがありました。 そういった背景があり、告知を見た時に「これだ!」と思い、参加することにしました。 建築業に携わっている身としても、建物の身体とも言える“木”について理解を深めることは非常に有意義です。建物資材だけではなく、薪、バイオマスエネルギーの燃料としても暮らしを支えてくれますし、木は暮らしを作る存在で重要な資源です。 加工された材料や商品としては、直ぐに手に取ることが出来ますが、その前の段階についてはあまり馴染みがありませんでしたし、林業の実態はなかなか知る機会もありませんでした。 森林は物理的に私たちのすぐそばにあり、存在するのが当たり前のようでありながら、これが「林業」となると、普段の生活から隔てられ、遠い存在であるように感じます。 今回のプログラムはその心理的距離を縮めてくれる、良い機会でした。 プログラムでの体験談 直径40cm、高さ25m近くの木を倒した時は、圧巻でした。 追い口という木を切り倒す最後の手順で、チェンソーを入れると、メキメ
松本の高晴天率という言葉から思う事
「松本の晴天率は高い」 先日、携わっている業務の関係で日中に市街地の景観写真を撮りに行きました。 午前中は曇天で昼ころから雲が切れて青空が見え始めてきましたが、突然雨が降ってきました。いわゆる天気雨です。 真上を見ると雲はなく、結構な勢いで、降る雨は周囲の雨雲から風で運ばれてきたような感じでした。四方は厚い雲で覆われ、頭上の空は抜けるような青。見慣れた風景ではありますが、これを見ながら「松本の晴天率は高い」という話を思い出しました。 統計上は松本の晴天率は全国でもトップクラスで、年間の日照時間はここ十年の平均で約2100時間。冬の降水量の少ない東京と比べても150時間ほど長いのです。 山に囲まれて日の出が遅く日の入り早い松本では、実際の差はもっと大きいと思います。 地域による気候差の大きい松本 ただ、現在の松本市は東は美ヶ原から西は乗鞍までと広く、個々の地域での気候の差は激しく、松本測候所と奈川測候所のデータでは気温で夏は4度、冬は3度ほど奈川の方が低いそうです。降水量は松本は年間平均で1000㎜程度なのに奈川は2000㎜と倍もあります。 それを考えると松本市と括っても平野部と山間部では日照時間も大きく隔たりがあり、まったく違う地域と考えてもいいくらいです。 松本における省エネ基準地域区分について、まとめ 少し話がそれますが、建物の断熱性能を決める省エネ基準地域区分では、以前は松本の中心部は4地域、旧安曇や波田、梓川といった西側の山間部は3地域に区分されていたのですが、2019年に改正があり松本は全地域が同じ4地域になりました。 日照時間が短く、気温も低くなる山間部で平野部と同じ基準で計算していいのはどうなんだろうと考えてしまいますが、基準はあくまで基準であると考えてケースバイケースで対応していくしかないのだろうと今は考えています。 もちろんオーナー様の意向もありますが、特に低温になる山間部では基準を満たすという事以上に性能を上げるべきか、念頭に置いて設計をするべきではと思っています。