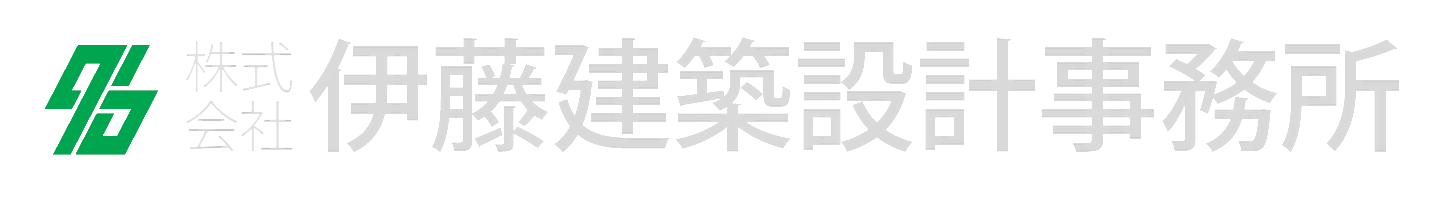今回は、本記事の担当者が参加した、長野県国営アルプスあづみの公園での水田作業と米作りのボランティアの体験談を共有していきます。
目次
「さとやま楽校 田んぼの教室」とは
今回私が参加した企画は「さとやま楽校田んぼの教室」は、長野県の国営アルプスあづみの公園の中の堀金・穂高地区で実施されているイベントです。2023年の企画に参加しました。
この「さとやま楽校 田んぼの教室」では、全6回の体験があります。(2024年時点)
以下のようなプログラムでした。
第1回 5月中旬頃 田植え
第2回 6月中旬~下旬頃 水田の除草作業
第3回 7月下旬頃 田んぼの生き物調査
第4回 9月上旬頃 稲刈り&はぜ掛け
第5回 9月下旬頃 脱穀・わら束づくり
第6回 10月中旬頃 新米炊き出しのお手伝い
泥だらけの田植え体験
ボランティア第1回目は田植えを行いました。私自身は小学生の頃に1度体験しましたが、かなり久しぶりの体験でした。
当日はとても天気も良く、田んぼの水はひんやりとしていて、足が泥だらけになりながらもとても清々しい気持ちで田植え作業ができました。
作業は参加者約40名を半分の2つのブロックに分け、約20名ずつのチームで行いました。
参加者が1列に横並びし、横に張られたロープを目印に自分の手の届く範囲の4列程度の苗を植え、全員が植え終わったらロープを前にずらし、また、自分の手の届く範囲の苗を植える、という事をひたすら繰り返していきました。
最初は夢中で楽しんでいたのですが、前に進むにつれて、疲労で足が思うように上がらなくなったり、腰が痛くなったり、前を見るとまだ先が長いことに本当に終わるのだろうかと感じたりしていました。
周りを見渡した時に、バランスを崩して転んでしまい、下半身と腕が泥だらけになりながらも頑張って田植えをしている子供がいたのが印象的でした。
水田にも雑草が生える!除草作業
田んぼの中には雑草は生えないと思い込んでいたのですが、雑草は生えるということ、さらにそれを除去しなければならないことを知ったのが第2回目の活動日でした。
私が参加した除草作業は2回に分かれた2回目の除草作業で、1回目は前の週に実施していたので、大きな雑草はほぼありませんでした。しかし、泥の地面をはいつくばっている雑草があり、その雑草を取り除くのが想像していたよりも大変で、田植えの時よりも疲れたような気がします。
除草の目的は、雑草を取り除く以外にも、稲の根に酸素を送り込むという目的もある事を教えて頂きました。
後に本を読んで知ったのですが、田んぼの中にコイを泳がせ泥を搔きまわし除草している所もあるようです。
水田に住む生き物
第3回の生き物調査は、私はスケジュールが合わず参加できませんでした。それでも他の回で、水田に住む生き物を観察することができました。
それは、除草作業の時に見かけたタガメのような、背中に粒状のものが付いている生き物で、今までに全く見たことのない虫でした。スタッフの方に尋ねるとコオイムシという生き物だということがわかりました。
背中の粒状のものは卵との事で、子を背負ってるのでコオイムシという名がついているようです。
準絶滅危惧の状況にある事もスタッフの話から知る事ができました。
稲刈り、はぜ掛け
第4回目の活動日には稲刈りとはぜ掛けを体験しました。
稲を刈った後、約2週間天日と風によって乾燥させます。こうしてお米を干すことで、アミノ酸と糖の含有量が高くなるそうです。また稲を逆さまに吊るすことで、わらの油分や栄養分、甘みが最下部の米粒へおりて、栄養とうま味が増すとのことです。
このはぜ掛けですが、地方によっては稲掛け(いねかけ)や稲架(とうか)など様々な呼び方があるようです。
脱穀・わら束づくり
第5回の脱穀・わら束づくりは、先日はぜ掛けした稲の束を機械の脱穀機に入れて、穂先から籾(もみ)を落とし、袋詰めしていきました。途中で雨が降ってきたのでやむなく中断してしまい、残りはスタッフの方たちが後日脱穀してくださいました。
最終回で自分たちが世話した米を食べる
第6回の新米炊き出しは、スタッフの方たちが、米のもみ殻(ぬか)を燃料にしたかまど「ぬかくど」を使って、お米を炊いて下さっていました。
参加者は出来上がったご飯を頂き、持ってきたおかずと一緒に食べるという楽しい回でした。自分も米作りに関わったからなのか、甘みの豊な新米のおいしさに感動しました。大満足の回でした。
雑感とまとめ
今回のボランティア活動では、参加者は数回の体験しかしていませんが、農家の方にとってはこれが毎日の作業。改めて農作業の大変さを身に染みて感じました。
今までも食べ物を粗末にしないように心がけてきたつもりですが、より一層、米のありがたみが増す経験となりました。
また、長野県でこういった気軽に参加できるボランティア活動の環境が整っていることは、大人だけでなく子供への食育という面でもありがたいことです。
最後に、今回農家の方が苗を購入して、自分たちの田んぼで米を栽培し出荷している姿に、建築設計事務所を重ねて見ている自分がいました。
私たち建築設計事務所も、他のメーカが製作した機器や材料を調達し、いろいろな設備と組み合わせて一つの施設や建物が完成するように設計、施工管理をした上で施主に引き渡すという点では、どこか似ている所もあると親近感が湧きました。