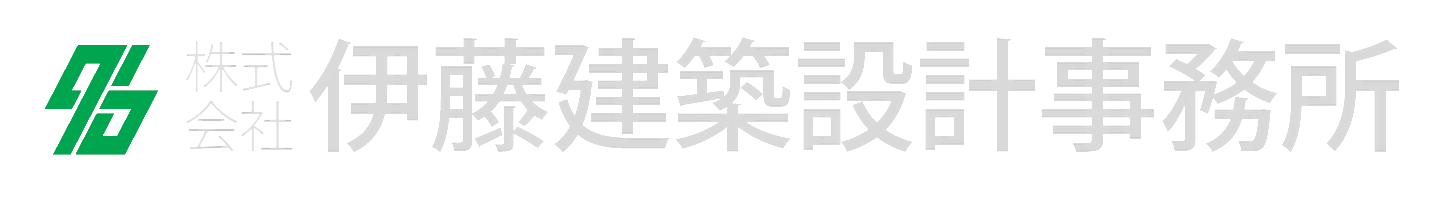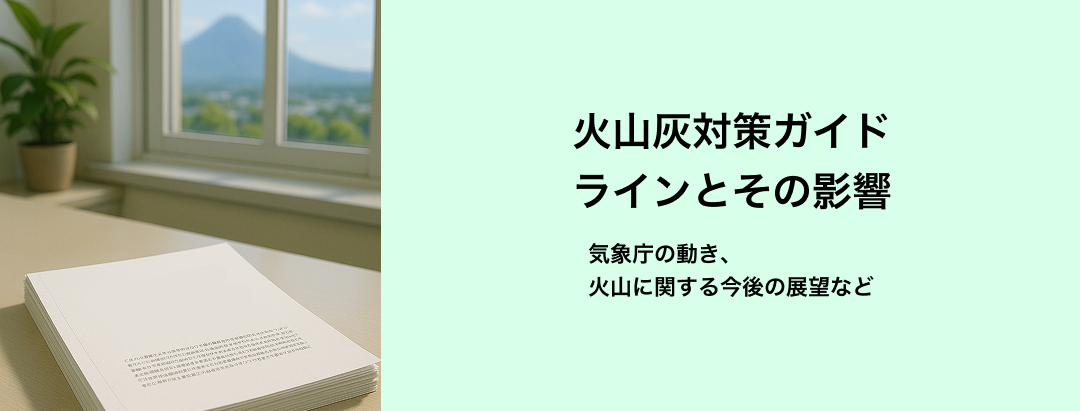
2025年3月30日、九州南部に位置する新燃岳(しんもえだけ)の噴火警戒レベルが2から3へ引き上げられ、その後も同レベルが継続しています。(2025年5月現在)このような火山活動の活発化を受けて、火山灰対策への関心が高まっています。今回は、富士山噴火を想定した降灰対策の取り組みを中心にご紹介します。
目次
降灰ステージの区分と対策の留意点
2025年3月21日、内閣府が発表した「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」では、降灰量に応じて4つの「ステージ」に分けた対策方針が示されました。特にステージ2から4においては、建物の損壊リスクや避難の必要性が具体的に記されています。
気象庁の動きと今後の課題・対策
気象庁の新たな情報と警報制度の改善
「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」発表翌週の3月25日には、気象庁の有識者検討会において、新たな火山灰情報の運用方針が了承されました。今後は、降灰量に応じて「火山灰警報」や「火山灰注意報」(いずれも仮称)が発表される見通しです。
今後の課題と対応策
火山灰情報の運用開始には数年かかると見られていますが、それまでの間も住民の備えや建築物の耐性確認など、日常的な対策が求められます。
過去の事例と今後の展望
富士山の例
日本最大の活火山・富士山に関しては、1707年の「宝永噴火」以来、300年以上噴火していません。これは過去5000年で最長の空白期間とされており、今後の噴火リスクが懸念されています。特に南海トラフ巨大地震との連動が注目されており、防災の観点からも建築設計における配慮が重要です。
生活への影響と備えが必要な理由
火山灰は、わずか0.1mmで鉄道の運行停止やぜんそくの悪化、3cmの灰で車の走行が困難になるなど、生活インフラに大きな影響を及ぼします。特に都市部では避難の現実性が乏しいため、各家庭が2週間分の生活物資を備蓄することが推奨されています。
現在本ブログの筆者は、自然災害に対する備えの大切さを改めて感じています。
火山活動がもたらすリスクに対し、建築設計や地域計画の面からも持続的な対応が求められます。社会全体で協力し、安全で安心なまちづくりを目指していく必要があります。