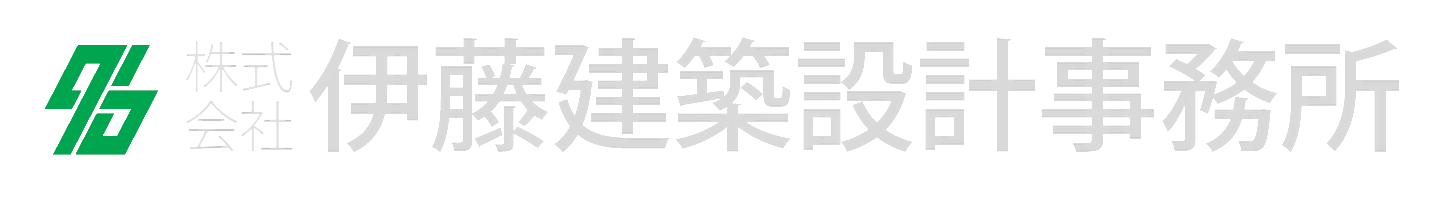誠に恐れ入りますが、弊社では2023年12月30日(土)から2024年1月4日(木)まで年末年始休業とさせていただきます。 勝手ながら、休業期間中はお電話でのお問い合わせはお休みさせていただきます。 メールでいただいたお問い合わせにつきましては、1月5日(金)以降順次対応させていただきますので、何卒ご了承のほどお願いいたします。 本年もお世話になりありがとうございました。 来年もどうぞよろしくお願いいたします。
福井県立恐竜博物館の見学
はじめに、見学の経緯 今年2023年の7月14日に改修工事が完了し、リニューアルオープンした福井県立恐竜博物館ですが、先日家族で行き、建物や貴重な展示品などを見学する機会がありましたので今日はそのレポートをお届けします。 ここは世界三大恐竜博物館の一つとされているようです。 私の子供が恐竜に興味を持ち、同時に私も少しずつ興味を持つようになっていたこともあり、いつか絶対に行ってみたいと思っていた場所でした。 建築物の概要 既存 建築物概要 所在地:福井県勝山市 竣工 :2000年6月 規模:建築面積 8,792㎡ 延床面積 15,086㎡ 構造 :SRC造 RC造 S造 階数 :地下1階 地上3階 + ドーム 寸法 :高さ約37.5m、長径 84m、短径 55m(ドーム) 設計 :黒川紀章建築都市設計事務所 改修工事の内容 大きな改修工事があったのは上記の写真、右側の建物についてです。 銀色の卵型ドームや大型スクリーンを3面備えた特別展示室、多目的ホール、また化石のクリーニングや骨格組み立てを楽しめる体験教室ゾーンの約400㎡が増設されました。 また、左側の既存棟も2,480㎡を対象に改築し、図書室やキッズルームを新設し、ショップ・レストランは2倍以上の広さに拡充したようです。 設計上の特徴 建物を航空写真で確認してみると、周囲の景観は豊かな森と田園風景であることが確認できます。 この設計では、緑豊かな自然の地形を極力保存しながら、山に根付いた自然と 一体化した建築を実現しているそうです。 地形の起伏を積極的に利用するために、建物は敷地の高低差の中に沈み込ませているのが特徴的です。 建物断面概略図で確認しても、出入口を3階に配置し、エスカレータで一気に地下1階へ接続する構成となっていることに気付かされます。 自然の地形を極力保存し起伏を積極的に利用しています。 山の斜面を一旦掘り込んで建設された後、北側が2階部分まで埋め戻されたため、隣接する北側壁には、館内に除湿用の空間が設けられているようです。 (参考資料:福井県立恐竜博物館ホームページ / 恐竜博物館の建物より) 内部の様子 利用者目線でのレポート 中へ入場した際に見える景色がこちらです。 中央のエスカレータで一気に地下へ下り、ダイノストリートと呼ばれる通路を経由して恐竜ホール棟の1階へアプローチする動
火災時に役立つ情報 まとめ
先日、現在設計中の波田小学校の児童約800名による避難訓練がありました。 今回はそれにちなんで、火災時に役立つ情報、避難や消火器の使い方などについて情報をまとめていきたいと思います。 火事の発見から避難までの流れ 火災の目撃や自火報等で発生が確認されたら、大声でみんなに知らせます。 状況に応じて初期消火を行うと同時に119番通報と避難誘導を行います。※火が天井に達していると初期消火は行わず、避難するのが良いとされています。 自力で避難できない人がいたら搬送します。 避難したら、逃げ遅れがないか確認します。 避難訓練の際はここまでで終了です。 消火器の使い方 皆さんの中には消火器を実際に使ったことのない方もいらっしゃると思います。そこでここでは消火器等の使い方などを詳しく見ていくことにしましょう。 事前に知っておくことの重要性 使い方は消火器の裏に書いてありますが、それを見ていては火災が広がってしまいます。初期消火には少しでも手順を覚えておくのが有効です。 消火器使用の手順 まず、避難用の出口を確保します 粉末消火器は上部の黄色い安全栓(ピン)を抜きます。 抜かないといくら握っても消火剤は出ません。 またホースを最初に(「ポン」と)外して火に向けます。外さないで握ってしまうと下に吹き出し、消火器が倒れるなどして消火が出来なくなります。なお工事現場などでよく見るパッケージ型消火設備の場合は、ホースが消火剤ボンベの周りに巻いてあるのでそれを外し、バルブを開けてからホース先端にあるノズルを開けて消火します。 パッケージ型消火設備前提として必ずこの二つを行ってから消火を開始するようにしましょう。 ホースを火に向け、消火を開始します。 消火は火元から3~5m程度離れて行います。炎の手前から箒で掃くように消火して、段々近づいて レバーを強く握る(「パン」と握る)ことで、消火剤が放射されます。ここまでの流れを、消防署のウェブサイトでは、「ピン」「ポン」「パン」と覚えておくと、忘れにくい旨が紹介されていました。 参考:四日市市消防本部ウェブサイト / 消火器の使い方 手前の下の方からホウキで履くようにホースを動かします。 炎が弱まってきたら、少しずつ火に近づきます。 その他の消火栓 改修工事の現場などでは、二人で操作するタイプの1号消火栓を目にすることも