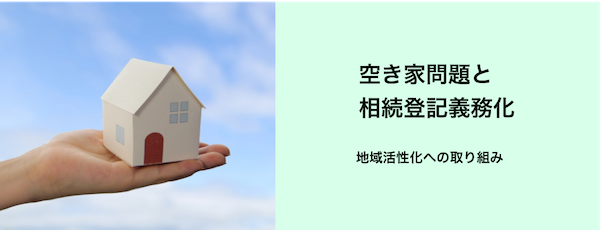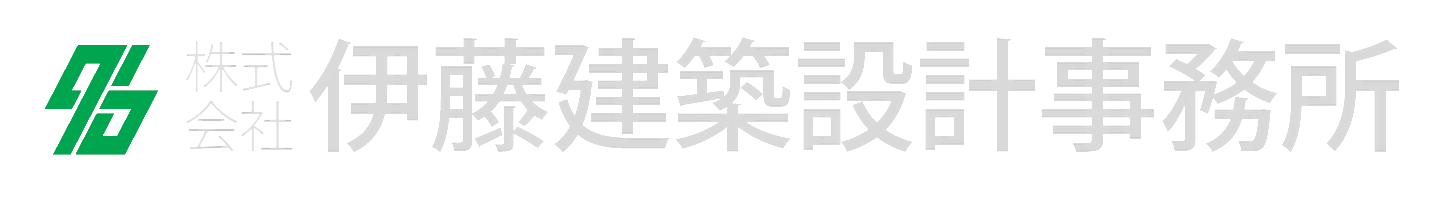今回は、全国地方各地で問題になっている空き家問題と、その課題解決、つまり地域活性化について、具体的にどんな取り組みが行われているかまとめていきます。 2024年に義務化された不動産の相続登記についても見ていきましょう。 空き家問題の現状 家族が減少し、高齢者が施設や病院に入るなどの理由で、全国各地で空き家が増えています。空き家の維持には草刈りなどの労力と費用がかかり、古くなると屋根や外壁が台風などで壊れ、近隣に迷惑をかけることもあります。また、家に人が住んでいないと家屋の傷みが進み、補修費用も増加します。 所有者不明土地の増加 所有者が亡くなっても相続登記がされていないため、「所有者不明土地」が全国で増加しています。これにより、周囲の環境悪化や公共事業の進行が妨げられるなど、社会問題が深刻化しています。 相続登記義務化の施行 2024年4月1日に相続登記義務化が施行されました。これにより、相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。 法務省ホームページより 正当な理由がないにも関わらず登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることになります。この義務化により、売りに出される物件が増えると予想されます。 空き家の統計と増加傾向 総務省の「住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)によると、日本の総住宅数は6502万戸で、2018年と比べて261万戸増加しています。全国の空き家数は900万戸と過去最多で、空き家率は13.8%と過去最高を記録しています。特に和歌山県、徳島県、山梨県、鹿児島県、高知県、長野県の空き家率が高く、地域差も顕著です。 松本市の空き家利活用促進 長野県松本市では、空き家バンク利活用促進事業補助金という制度があり、最大で105万円の補助が受けられます。この制度を活用して、空き家をカフェやゲストハウスに改装する事例が増えています。空き家を有効活用することで、周囲の景観改善や治安向上、地域の活性化が期待されます。 空き家問題の解決と地域活性化 (まとめ) 空き家問題は私たちの身近な課題です。相続登記義務化や補助金制度を活用し、空き家の有効活用を推進することで、地域社会の発展に貢献でき課題解決につながります。 弊社もこの問
米作りのボランティア体験記
今回は、本記事の担当者が参加した、長野県国営アルプスあづみの公園での水田作業と米作りのボランティアの体験談を共有していきます。 「さとやま楽校 田んぼの教室」とは 今回私が参加した企画は「さとやま楽校田んぼの教室」は、長野県の国営アルプスあづみの公園の中の堀金・穂高地区で実施されているイベントです。2023年の企画に参加しました。 この「さとやま楽校 田んぼの教室」では、全6回の体験があります。(2024年時点) 以下のようなプログラムでした。 第1回 5月中旬頃 田植え 第2回 6月中旬~下旬頃 水田の除草作業 第3回 7月下旬頃 田んぼの生き物調査 第4回 9月上旬頃 稲刈り&はぜ掛け 第5回 9月下旬頃 脱穀・わら束づくり 第6回 10月中旬頃 新米炊き出しのお手伝い 泥だらけの田植え体験 ボランティア第1回目は田植えを行いました。私自身は小学生の頃に1度体験しましたが、かなり久しぶりの体験でした。 当日はとても天気も良く、田んぼの水はひんやりとしていて、足が泥だらけになりながらもとても清々しい気持ちで田植え作業ができました。 作業は参加者約40名を半分の2つのブロックに分け、約20名ずつのチームで行いました。 参加者が1列に横並びし、横に張られたロープを目印に自分の手の届く範囲の4列程度の苗を植え、全員が植え終わったらロープを前にずらし、また、自分の手の届く範囲の苗を植える、という事をひたすら繰り返していきました。 最初は夢中で楽しんでいたのですが、前に進むにつれて、疲労で足が思うように上がらなくなったり、腰が痛くなったり、前を見るとまだ先が長いことに本当に終わるのだろうかと感じたりしていました。 周りを見渡した時に、バランスを崩して転んでしまい、下半身と腕が泥だらけになりながらも頑張って田植えをしている子供がいたのが印象的でした。 水田にも雑草が生える!除草作業 田んぼの中には雑草は生えないと思い込んでいたのですが、雑草は生えるということ、さらにそれを除去しなければならないことを知ったのが第2回目の活動日でした。 私が参加した除草作業は2回に分かれた2回目の除草作業で、1回目は前の週に実施していたので、大きな雑草はほぼありませんでした。しかし、泥の地面をはいつくばっている雑
家庭で簡単にできる雑菌・カビ対策
皆さんはご家庭でカビや雑菌対策を意識した掃除をしていますか。 今回は梅雨時などは特に気をつけたいカビや雑菌の繁殖について、ご家庭で簡単にできる対策をご紹介します。 台所・シンクの雑菌対策 『シンクが汚い』という悩みは、汚れを放置してしまうために悪化しているケースが多いようです。 シンクにつく汚れは、お皿と一緒で、食材や油分がほとんどです。そのため、食器を洗ったあと、毎回簡単にスポンジと洗剤でさっと洗うと良いでしょう。 わざわざ分けようとすると面倒に感じてしまい継続できないので、筆者の家庭ではシンクも食器と同じという考え方で行っています。もともと汚れていなければ1分半ぐらいで終わります。 シンクが常に清潔に保たれていれば、洗った野菜なども直置きできます。 蛇口も常に水にさらされて湿気がある上、洗剤や食材などが飛び跳ねた際に付着しやすく、カビが発生しやすい部分です。蛇口を大きくひねって大量の水を流すだけでは取り除きにくいため、定期的にこすり洗いをする必要があります。 お風呂の雑菌対策 お風呂掃除は、浴槽内の清掃や空気の入れ替えなどは手が届きやすいですが、壁や床まで掃除するとなると毎日時間を確保するのは難しい方は多いのではないでしょうか。 なかなか掃除できないことがわかっている場合は、いかにカビを防止するかという考え方に切り替え、設計時に綺麗に保ちやすい素材を選べると理想的です。 手軽にできる方法として、最近ではカビ防止シールなども売っていますので、それを活用すると便利です。 日々のこまめな気遣いとしては、お風呂から出る時に壁や床の水垢や皮脂をお湯のシャワーで流したあと、水のシャワーで流し、室内温度を下げるのがカビ減少に効果的です。 洗濯機の雑菌対策 洗濯機の中にイヤなニオイがあったり、洗濯物を干すときに黒いカスがついていたりすることがあります。これは、洗濯槽の裏側についたカビなどが原因です。 乾いた衣類をしまう時にパンパンとすると飛び散ります。 対策として、3ヶ月に1回程度専用クリーナーを入れて回すだけで予防が出来ます。旧式でステンレス槽でない洗濯機はクリーナーでのメンテナンス回数を増やすなどで対応すれば良いでしょう。 また洗剤入れなどにも水滴はついているので、そういったものもその都度外して乾かすことで清潔に保てます。 &nb
バイオミミクリー(生物模倣)建築
今回は、自然界の仕組みを模倣した建築、バイオミミクリー(生物模倣)建築についてです。 バイオミミクリーとは何か、そしてバイオミミクリー建築の代表例としてアフリカ・ジンバブエの「 Eastgate Center(イーストゲート・センター)」を紹介していきます。 バイオミミクリー(生物模倣) とは何か バイオミミクリーやバイオミメティクスと言う言葉を聞いたことがありますか? これらの言葉は日本語で「生物模倣」「生物模倣技術」と訳すことができ、生物の体型・色・機能・行動など様々 な要素を模倣し技術開発に活かそうとする科学技術のことです。 生物模倣の歴史は古く、有名な事例としてはレオナルド・ダヴィンチ(1452–1519)がコウモリの翼を模倣した空飛ぶ機械を設計していたこと(当時はアイディアのみで実用化はできなかった)、またライト兄弟が、1903年にハトからインスピレーションを得た「飛行機」の飛行に成功したことなどが挙げられます。 また最近では、蚊の針を参考に作った「痛くない注射針」なども有名です。 バイオミミクリー(生物模倣) 建築 以上で見てきた生物模倣技術ですが建築業界では、「バイオミミクリー」の言葉を使うことが多く、生物模倣を取り入れた建築のことをバイオミミク リー建築と称します。 生物は、進化の過程で絶えず変化する環境に適応してきました。最近では持続可能性の観点から、生物模倣の哲学が注目されており、エネルギー効率の改良などの面でも期待が高まっています。 バイオミミクリー(生物模倣)実例: 建築 Eastgate Center(イーストゲート・センター) 概要 バイオミミクリー建築の代表格のひとつが、アフリカ大陸ジンバブエの首都ハラーレに建つショッピングモール「 Eastgate Center(イーストゲート・センター)」です。 設計は地元出身の建築家:Mick Pearce(ミック・ピアース)で1996年に完成しました。 【写真と参考】 Watch how the Eastgate Center in Zimbabwe Cools Itself Without Air Conditioning https://livinspaces.net/ls-tv/watch-how-the-eastgate-center-in