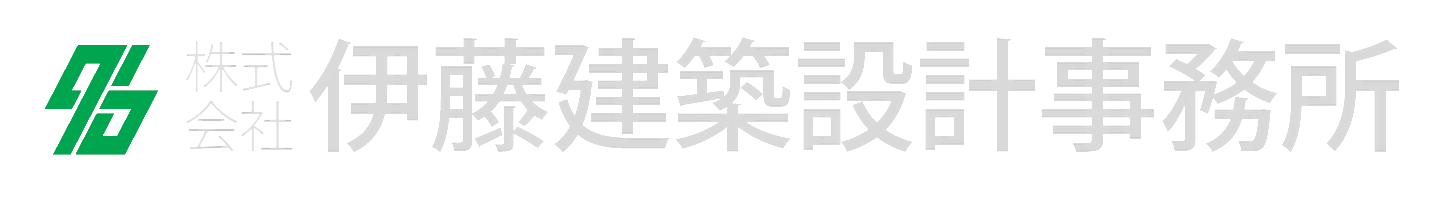誠に恐れ入りますが、弊社では2023年12月30日(土)から2024年1月4日(木)まで年末年始休業とさせていただきます。 勝手ながら、休業期間中はお電話でのお問い合わせはお休みさせていただきます。 メールでいただいたお問い合わせにつきましては、1月5日(金)以降順次対応させていただきますので、何卒ご了承のほどお願いいたします。 本年もお世話になりありがとうございました。 来年もどうぞよろしくお願いいたします。
福井県立恐竜博物館の見学
はじめに、見学の経緯 今年2023年の7月14日に改修工事が完了し、リニューアルオープンした福井県立恐竜博物館ですが、先日家族で行き、建物や貴重な展示品などを見学する機会がありましたので今日はそのレポートをお届けします。 ここは世界三大恐竜博物館の一つとされているようです。 私の子供が恐竜に興味を持ち、同時に私も少しずつ興味を持つようになっていたこともあり、いつか絶対に行ってみたいと思っていた場所でした。 建築物の概要 既存 建築物概要 所在地:福井県勝山市 竣工 :2000年6月 規模:建築面積 8,792㎡ 延床面積 15,086㎡ 構造 :SRC造 RC造 S造 階数 :地下1階 地上3階 + ドーム 寸法 :高さ約37.5m、長径 84m、短径 55m(ドーム) 設計 :黒川紀章建築都市設計事務所 改修工事の内容 大きな改修工事があったのは上記の写真、右側の建物についてです。 銀色の卵型ドームや大型スクリーンを3面備えた特別展示室、多目的ホール、また化石のクリーニングや骨格組み立てを楽しめる体験教室ゾーンの約400㎡が増設されました。 また、左側の既存棟も2,480㎡を対象に改築し、図書室やキッズルームを新設し、ショップ・レストランは2倍以上の広さに拡充したようです。 設計上の特徴 建物を航空写真で確認してみると、周囲の景観は豊かな森と田園風景であることが確認できます。 この設計では、緑豊かな自然の地形を極力保存しながら、山に根付いた自然と 一体化した建築を実現しているそうです。 地形の起伏を積極的に利用するために、建物は敷地の高低差の中に沈み込ませているのが特徴的です。 建物断面概略図で確認しても、出入口を3階に配置し、エスカレータで一気に地下1階へ接続する構成となっていることに気付かされます。 自然の地形を極力保存し起伏を積極的に利用しています。 山の斜面を一旦掘り込んで建設された後、北側が2階部分まで埋め戻されたため、隣接する北側壁には、館内に除湿用の空間が設けられているようです。 (参考資料:福井県立恐竜博物館ホームページ / 恐竜博物館の建物より) 内部の様子 利用者目線でのレポート 中へ入場した際に見える景色がこちらです。 中央のエスカレータで一気に地下へ下り、ダイノストリートと呼ばれる通路を経由して恐竜ホール棟の1階へアプローチする動
火災時に役立つ情報 まとめ
先日、現在設計中の波田小学校の児童約800名による避難訓練がありました。 今回はそれにちなんで、火災時に役立つ情報、避難や消火器の使い方などについて情報をまとめていきたいと思います。 火事の発見から避難までの流れ 火災の目撃や自火報等で発生が確認されたら、大声でみんなに知らせます。 状況に応じて初期消火を行うと同時に119番通報と避難誘導を行います。※火が天井に達していると初期消火は行わず、避難するのが良いとされています。 自力で避難できない人がいたら搬送します。 避難したら、逃げ遅れがないか確認します。 避難訓練の際はここまでで終了です。 消火器の使い方 皆さんの中には消火器を実際に使ったことのない方もいらっしゃると思います。そこでここでは消火器等の使い方などを詳しく見ていくことにしましょう。 事前に知っておくことの重要性 使い方は消火器の裏に書いてありますが、それを見ていては火災が広がってしまいます。初期消火には少しでも手順を覚えておくのが有効です。 消火器使用の手順 まず、避難用の出口を確保します 粉末消火器は上部の黄色い安全栓(ピン)を抜きます。 抜かないといくら握っても消火剤は出ません。 またホースを最初に(「ポン」と)外して火に向けます。外さないで握ってしまうと下に吹き出し、消火器が倒れるなどして消火が出来なくなります。なお工事現場などでよく見るパッケージ型消火設備の場合は、ホースが消火剤ボンベの周りに巻いてあるのでそれを外し、バルブを開けてからホース先端にあるノズルを開けて消火します。 パッケージ型消火設備前提として必ずこの二つを行ってから消火を開始するようにしましょう。 ホースを火に向け、消火を開始します。 消火は火元から3~5m程度離れて行います。炎の手前から箒で掃くように消火して、段々近づいて レバーを強く握る(「パン」と握る)ことで、消火剤が放射されます。ここまでの流れを、消防署のウェブサイトでは、「ピン」「ポン」「パン」と覚えておくと、忘れにくい旨が紹介されていました。 参考:四日市市消防本部ウェブサイト / 消火器の使い方 手前の下の方からホウキで履くようにホースを動かします。 炎が弱まってきたら、少しずつ火に近づきます。 その他の消火栓 改修工事の現場などでは、二人で操作するタイプの1号消火栓を目にすることも
福島への旅と建築
先日、休みを利用して福島県へ旅行に行ってきました。 その旅行レポートを建築的な側面にスポットを当てながらお話ししていきます。 会津若松のさざえ堂 集合は郡山駅。松本からは片道4時間ほどで、なかなか遠い道のりでした。 郡山で集合後、会津若松に向かいました。 さざえ堂や白虎隊の石碑などを見て、戊辰(ぼしん)戦争に思いを馳せました。 左の写真の階段を登ったところにさざえ堂があります。 さざえ堂は二重構造のらせん階段を持ち、お堂としては珍しい建築様式を採用しており、国の重要文化財に指定されています。 さざえ堂はもともと三十三観音が安置され巡礼を行える場所でしたが、今では観音様はおらず13の偉人が奉られています。 新宮熊野神社 そこから北に向かい、新宮熊野神社へ向かいます。 目当ては熊野神社の拝殿にあたる「長床 (ながとこ)」という建築物です。 この長床という施設は熊野系の神社に多く見られ、拝殿としてだけでなく、修行僧の修行の場や、旅人の宿として利用されていたようです。 今回訪れた長床は、平安時代の寝殿造りの建築物であり、直径1尺5寸の円柱44本を5列並べて構成されています。 まさに「繰り返しの美学 ※」を感じるとともに、1尺5寸の柱の重厚さ、がらんどうであることで拝殿、修行、宿泊宿などの複雑な機能を受け入れられるフレキシブルな空間は、現代建築にも参照できるところが多いと感じました。 ※繰り返しの美学、繰り返しの手法の面白さについては以前こちらの記事でも取り上げています。 はじまりの美術館 猪苗代湖近くの宿で一泊して二日目、少し時間があったので小さな美術館に立ち寄りました。 その名も「はじまりの美術館」です。 この美術館は障がい者支援を行う社会福祉法人が、東日本大震災後の復興の一環として築100年以上の酒蔵をリノベーションして建てられました。その酒蔵は「十八間蔵」と称される通り桁行十八間ある蔵で、既存当時は一本ものの梁があったとのことでした。今は2本の梁を継いでいますが、それでも独特な空間を感じることができます。 内部も殴り仕上げの無垢フローリングや、小端立ての床材など、思わず裸足で歩いてみたくなるような楽しく気持ちの良い場所でした。 マテリアル重視で、建物全体がアート空間であるかのように感じました。 展示内容は現
林業プログラム「kikori塾」について
今日は、私が参加している「kikori塾」という林業プログラムについてのお話です。 kikori塾はどんなプログラムか プログラムは、1回のプログラムで2日間、全部で三回行われます。 ※現在この記事を執筆している時点では2回目を終えており、残すところあと一回です。 このプログラムは、南アルプスの景観が広がる伊那市で行われています。 伊那市の協力のもと、民間の林業従事者であるきこりから、山仕事や、木の植生を学びます。 実際に山に入り、間伐材をチェンソーで使って切り倒し、枝払いを行い、山から運びだします。その後、薪や合板、加工品として商品となる過程をお手伝いしながら、山暮らしを体験していきます。 参考外部サイト: https://smout.jp/plans/11703 なぜ参加したのか このプログラムに参加するきっかけは、SNSの広告でした。ちょうどその頃、再生可能エネルギー、ゼロカーボン、といったキーワードについて、いち個人単位で、どんな活動が出来るのだろうかと考えていました。 また、林業の実態はどんなものだろうかと興味を持っていたことも理由です。林業の抱える課題は「担い手となる人材不足」「森が荒れ放題であること」などといったことを良く耳にしていましたが、リアルな現状を知りたいという思いがありました。 そういった背景があり、告知を見た時に「これだ!」と思い、参加することにしました。 建築業に携わっている身としても、建物の身体とも言える“木”について理解を深めることは非常に有意義です。建物資材だけではなく、薪、バイオマスエネルギーの燃料としても暮らしを支えてくれますし、木は暮らしを作る存在で重要な資源です。 加工された材料や商品としては、直ぐに手に取ることが出来ますが、その前の段階についてはあまり馴染みがありませんでしたし、林業の実態はなかなか知る機会もありませんでした。 森林は物理的に私たちのすぐそばにあり、存在するのが当たり前のようでありながら、これが「林業」となると、普段の生活から隔てられ、遠い存在であるように感じます。 今回のプログラムはその心理的距離を縮めてくれる、良い機会でした。 プログラムでの体験談 直径40cm、高さ25m近くの木を倒した時は、圧巻でした。 追い口という木を切り倒す最後の手順で、チェンソーを入れると、メキメ
松本の高晴天率という言葉から思う事
「松本の晴天率は高い」 先日、携わっている業務の関係で日中に市街地の景観写真を撮りに行きました。 午前中は曇天で昼ころから雲が切れて青空が見え始めてきましたが、突然雨が降ってきました。いわゆる天気雨です。 真上を見ると雲はなく、結構な勢いで、降る雨は周囲の雨雲から風で運ばれてきたような感じでした。四方は厚い雲で覆われ、頭上の空は抜けるような青。見慣れた風景ではありますが、これを見ながら「松本の晴天率は高い」という話を思い出しました。 統計上は松本の晴天率は全国でもトップクラスで、年間の日照時間はここ十年の平均で約2100時間。冬の降水量の少ない東京と比べても150時間ほど長いのです。 山に囲まれて日の出が遅く日の入り早い松本では、実際の差はもっと大きいと思います。 地域による気候差の大きい松本 ただ、現在の松本市は東は美ヶ原から西は乗鞍までと広く、個々の地域での気候の差は激しく、松本測候所と奈川測候所のデータでは気温で夏は4度、冬は3度ほど奈川の方が低いそうです。降水量は松本は年間平均で1000㎜程度なのに奈川は2000㎜と倍もあります。 それを考えると松本市と括っても平野部と山間部では日照時間も大きく隔たりがあり、まったく違う地域と考えてもいいくらいです。 松本における省エネ基準地域区分について、まとめ 少し話がそれますが、建物の断熱性能を決める省エネ基準地域区分では、以前は松本の中心部は4地域、旧安曇や波田、梓川といった西側の山間部は3地域に区分されていたのですが、2019年に改正があり松本は全地域が同じ4地域になりました。 日照時間が短く、気温も低くなる山間部で平野部と同じ基準で計算していいのはどうなんだろうと考えてしまいますが、基準はあくまで基準であると考えてケースバイケースで対応していくしかないのだろうと今は考えています。 もちろんオーナー様の意向もありますが、特に低温になる山間部では基準を満たすという事以上に性能を上げるべきか、念頭に置いて設計をするべきではと思っています。
ハイブリッドニーディング工法とは
この記事では、マンションの既製コンクリート杭などに採用されるハイブリッドニーディング工法とはなにか、解説していきます。また弊社での取り扱い事例も一部ご紹介します。 建築現場で使用される杭の施工法を種類別に紹介 施工方法で大まかに2種類に分類できる 杭工事は施工方法で分類すると、 ・既製杭工法 ・現場打ちコンクリート杭工法 に分けられます。 図から分かるように、既製杭工法では、別の工場で作られた電信柱のようなコンクリート柱を杭として埋め込む方法です。一方で現場打ち杭工法は、あらかじめ開けた穴に鉄筋で組んだカゴのようなものを入れ、そこにコンクリートを流し込むという方法です。 また、上の図から分かるように、既製コンクリート杭の中には3種類の杭工法があります。 その3種類とは 打ち込み杭工法 埋め込み杭工法 回転杭工法 です。 それぞれの杭の特徴 打込み杭:支持力は大きいが、施工時に振動や騒音がある。このデメリットのため、最近はあまり採用されない傾向がある。 埋め込み杭:支持力については、打ち込み杭よりは支持力は小さいが、現場打ち杭よりは大きい。振動や騒音も打ち込み杭に比べると小さい。さまざまな工法の中でも、いろいろな要素が中間的である工法。 回転杭:先端に羽根を取り付けた鋼管杭に回転力を付与し、地盤に貫入させる工法。 無騒音・無振動で施工できるが、地盤がに硬い石や異物が多く入っている場合、回転羽が破損する可能性がある。 なお、今回テーマとして取り上げたハイブリッドニーディング工法は、既製杭工法で、埋め込み杭です。 言葉の意味 ハイブリッドニーディングというとなかなか聞きなれない言葉ですが、 「ハイブリッド」は、異なる2つの要素、方式が組み合わさったもの、またはそのような性質を持つものを指し、「ニーディング」は英語で、こねたり練ったりすることを指します。 言葉の意味を見ることで、この方法のイメージが掴みやすくなったのではないでしょうか。 ハイブリッドニーディング工法とは ハイブリッドニーディング工法の概要 ハイブリッドニーディング工法はその言葉の意味からも分かるように、種類の違う杭を繋げて使用する工法です。 基本的に下杭には、節杭、または拡頭節杭、あるいは頭部厚型節付き杭など
デジタルスタンプラリーとは
デジタルスタンプラリーとは、従来のスタンプラリーを現代式にしたスタンプラリーで、スマートフォンやタブレットを使ってスタンプを取得できるタイプのスタンプラリーです。 今回は、最近地域活性化のため各所で盛んに行われているデジタルスタンプラリーについてまとめてみました。(※本記事は2023年現在の情報です) 長野県で見かけた身近な例 先日見かけたのは、こちらのデジタルスタンプラリーです。 ジャパンエコトラック八ヶ岳・諏訪湖 デジタルスタンプラリー2023 (https://www.japanecotrack.net/special/10) 松本駅のコンコースで、ポスターを見かけて存在を知りました。 このスタンプラリーの特徴は、公式アプリを使用することでデジタル式のスタンプラリーに参加できるということ。「ジャパンエコトラック八ヶ岳・諏訪湖」に登録されたルートを通過すると、自動的にデジタルスタンプが獲得でき、ルートを完走した際には完走の証であるデジタルバッジが獲得できるそうです。 また、完走してデジタルバッジを獲得して、アンケートに答えると、プレゼント抽選にも応募できるという特典があります。 他にもJR東日本主催で、人気アニメとコラボしたデジタルスタンプラリーを最近見かけました。 JR東日本 クレヨンしんちゃんスタンプラリー 参考URL: https://www.jreast.co.jp/crayonrally2023/ スタンプラリーはもう古い?!スマートフォン使用のデジタルラリーが普及 先の例に限らず最近では、スタンプラリーといえば、スマートフォンを利用したデジタルスタンプラリーの方が一般的になってきているようです。これにより、もう紙の台紙を持ち歩く必要はなくなります。 デジタルラリーの基本的な使い方 デジタルラリーの参加には、スマートフォンやモバイル端末の使用が必須です。 専用のアプリをインストールする、あるいは該当のWebページに行くことで、参加できます。 デジタルラリーに参加したら、その後は指定のルートの中のチェックポイントに実際に行きデジタルスタンプを取得します。ルート内にあるすべてのスタンプを集めて完走すると、プレゼントの抽選に応募することができます。 デジタルラリーの参加方法と使い方は基本的にどの企画もほぼ同じです。
京都・西本願寺訪問レポート
2023年の4月に、本ブログ記事筆者が個人的に京都の西本願寺を訪問しました。 今回は「慶賛法要(きょうさんほうよう)」という法要に参列したり、お寺の修復や瓦の様子について見る機会があったりしたので、そのレポートをお届けします。 はじめに 私が瓦に興味を持っている訳 この記事の筆者である私の親族には鬼瓦職人がおり、幼い頃より瓦に親しみがあります。必然的に瓦に注目することが多くなっていますが悪しからず。 西本願寺の概要 西本願寺(にしほんがんじ)は、京都にある浄土真宗本願寺派の本山の寺院で、正式名称は龍谷山 本願寺と言います。 境内には国の国宝、重要文化財などが数多く存在しており、西本願寺自体も「古都京都の文化財」としてユネスコより世界文化遺産に登録されています。 慶賛法要(きょうさんほうよう) 慶賛法要(きょうさんほうよう)とは? 今回2023年4月に私が参列した「慶賛法要」は親鸞聖人御誕生と立教開宗を慶び讃える御仏事です。 今年は親鸞聖人御誕生850年、立教改修800年という節目の年のお祝いでした。 慶賛法要(きょうさんほうよう)の様子 慶賛法要は西本願寺の御影堂(ごえいどう)で行われました。御影堂は、西本願寺の中でも国宝に指定されている建物の一つです。 以下の写真が御影堂です。 御影堂の中には椅子が数百並んでおり、全国から来た参加者に見えるよう、大型モニターが何台も養生された柱に設置されていました。 法要の中には本格的な雅楽も含まれており、貴重な体験でした。 西本願寺で見学した建築物、屋根と鬼瓦 法要の前後で、西本願寺を見学しました。 大玄関門の鬼瓦です。 ちなみに法要を行った御影堂(ごえいどう)や、寺院で良く見られる鬼瓦についてよく知らなかったので、帰ってから調べてみました。鬼瓦の代わりの獅子口(ししぐち)というそうです。(以下の写真参照) 上に「経の巻」という巴瓦を3つつけています。 御影堂の屋根の建築的解説 以下は御影堂(ごえいどう)の屋根です。 青字・青枠線部分の棟ですが、下から軒先の巴瓦を使った「甍 (いらか)」、「割熨斗瓦(わりのしがわら)」が何重もあり、最上部に冠瓦があります。 赤字・赤枠線部分は、獅子口(ししぐち)の下、妻側が蓑甲(みのこう)です。 その横の緑の部分は降棟(くだりむね)と言い
建築用3Dプリンターの活用
昨今3Dプリンターがものづくりの現場で話題になっていますが、建築の現場での導入も進んでいます。今日は、国内での住宅への3Dプリンター導入事例と、導入の際には具体的にどうするのかなどをご紹介します。また導入のメリットについても考えてみたいと思います。 3Dプリンターで作った住宅の国内事例 3Dプリンターと言えば、模型など立体造形への使用が代表的と思われがちですが、建築の現場での導入事例も出てきました。 例えば兵庫県西宮市のベンチャー企業・セレンディクス社は、「3Dプリンターで作る住宅」というコンセプトを打ち出し、2023年8月に、費用は550万円、工期は2日という前代未聞の手軽な住宅の販売を始められています。 [参考] セレンディックス社ホームページ https://serendix.jp/ 建築用3Dプリンターの導入方法 それでは建築用3Dプリンターが、具体的にどのように建築の現場で使われるのかを見ていきましょう。 代表的な建築方法は以下の2点です。 方法1:工場で部材を作って現場に運ぶパターン これは、建築用の3Dプリンターを導入している工場で、分割した建築物の部材を印刷する方法です。 出来上がった部材は建築現場へ持ち込み、基礎の上に組み立てて施工を行います。部材を組み立てたあとは、屋根や骨組みを加えていきます。部材を印刷している間は、並行して現場で基礎を施工できるため、施工期間が少なく済みます。 方法2:大型3Dプリンターを現場に設置するパターン こちら2つ目は、大型の3Dプリンターを直接建築現場に設置し、材料を積み重ねて施工する方法です。 従来の建築方法では、多くの職人や時間を必要としましたが、建築用の3Dプリンターを用いた場合は、少ない人数かつ短期間の施工が可能です。 中には直接3Dプリンターで建築を行うのではなく、コンクリート柱を建設するために、型枠を造形するモデルもあります。 建築の現場で3Dプリンターを使用するメリット 建築用3Dプリンターを使用する工法では、従来の工法と比べて以下のメリットが得られます。 メリット1:施工期間の短縮 建築用3Dプリンターを使用すると、従来の工法に比べて施行期間を大幅に短縮できるのが一つ目のメリットです。過去には24時間未満で住宅が建築された事例もあったほどでした。そのため、災害などで突然住
改正建築基準法 変更点まとめ
2025年4月に改正建築基準法や改正建築物省エネ法が施行されます。これにより建築のルールが大幅に変わります。 今回の記事では、改訂のポイントをまとめます。具体的に何が変わるのかを、簡潔に要点を押さえて紹介していきます。 四号特例(建築基準法)の見直し まず、四号特例(建築基準法)の見直しにより、構造計算が必要な延べ面積が変更になります。木造住宅などは特に影響を受けるので、該当する場合は注意が必要です。 審査省略の対象が変更 上の図の水色の箇所から分かるように、審査対象の建物の延べ面積が変わります。 審査省略対象の範囲が小さくなり、今までより厳しくなる印象があります。 具体的には、改正後は平屋の200㎡以内の建物のみ審査省略対象ということなります。 構造計算が必要なケースの変更 また、上の図のオレンジ色の箇所から分かるように、木造の場合、構造計算が必要になる延べ面積は 【改正前】500㎡以上 → 【改正後】300㎡以上 となります。 基準が厳しくなり、対象建物が増えることを意味しています。 他にも変更はあり、例えばルート3など高度な計算方法が必要となる建物規模については、以下のように見直されます。 【改正前】軒高9m、高さ13m超え→【改正後】4階建てまたは高さ16 m超え これに関しては、どちらかといえば緩和の方向に向かいます。 なお、今年(2023年)の秋頃に、申請に必要な構造関係規定の図書の種類等が規定される予定です。 省エネ基準の義務づけ また、省エネ基準がすべての建物に義務付けられます。 これについても今年(2023年)の秋頃に、申請に必要な省エネ関連の図書の種類等が規定される予定です。 省エネ義務化により建物重量が増大するため、構造基準も同時に改正されます。以下の章で詳しく見ていきましょう。 構造基準の変更 前述したとおり、省エネ義務化による建物重量の増大を受けて、壁量、柱の小径の基準が改定されます。 すでに去年(2022年)の10月にZEH水準等の建物の基準案が公表されていますが、今年(2023年)の秋ごろより順次、施行令の改正や、告示が公布されてゆく予定で、細かい内容はこれから明らかになります。 改正の概要について基準案では、壁量の規定は以下の3種類の方法が示されています。 <方法①> 荷重の
愛されるブランド 調査結果を読み解く
「ファンを魅了する愛されるブランド」の調査結果 まず、最初に以下の表を見てください。 この表は「ファンを魅了する愛されるブランド」いわゆるファン度をパーセンテージで表したものです。(2022年4~5月、ファン総合研究所が実施) インターネット上でアンケートを行い、その中で「このブランドが好きか」や「これからもずっと応援していきたいか」などの設問から、どのくらいの割合の人が該当ブランドのファンなのかを算出しています。 この調査では、対象を7業界47ブランドとしています。 7業界の内訳は、ビール業界、お菓子業界、清涼飲料業界、ファーストフード業界、家電業界、化粧品業界、コンビニエンスストア業界です。 まとめると、この表では、調査の中でコアファンとファンの割合がトップだった企業を列挙しています。 ※一番右の列の【 】内の数字は業界平均のパーセンテージです。 調査の中では以下の4項目に関する質問を中心にアンケートを実施しています。 利用頻度 利用金額 NPS(顧客満足度) ブランドに対する価値や意向 また、別の指標として、 機能価値 情緒価値 未来価値(社会・未来に対するポジティブなイメージ) 上記の価値を図る指標も設けたそうです。 それでは以上の表の結果について、調査中にあったコメントや、ファンが支持する理由等を詳しく見ていきましょう。 主力商品がそのままコーポレートイメージになった例 アサヒビール ビール業界1位はアサヒビール。コアファンとファンの割合が32.1%でした。(業界平均は27.7%) 回答者からは「自分の生きがい」「これ以上至福を感じる飲み物は他にはない」といった高評価が寄せられたそうです。 同社はビールだけでも複数ブランドを展開していますが、「日本のビールといえばアサヒスーパードライ」という回答があったことからもわかるように、不動の主力商品がそのままコーポレートイメージにつながっているようです。 「あなたにとってのアサヒビールの存在は?」という質問に対し、 「相棒」「人生の伴侶」など単なる消費財を超えた、身近で深い関係を築いていることがうかがえます。「また父が大好きだった。晩酌はいつもこれだった」と親の影響を受けているファンの声もありました。 「昔から変わらない」が「安心」のイメージにつながった例 ブルボン 菓子
繰り返しの手法の面白さ
皆さんは、とある形の屋根やパーツが何度も繰り返されている様式の建築をご覧になったことがありますか? 繰り返しの技法を使うことで、建物に独特な個性が生まれます。 今回は、筆者である私が好きな、建築における「繰り返し」の手法のついて、その面白さを解説していきます。 「繰り返し」の手法が使われている建物コレクション 東京の銀座線渋谷駅の新しい駅舎 写真は、こちら (東京メトロのウェブサイト)を参照ください。 波形の形状が繰り返され、目を引く印象的なデザインです。 駅の機能上、駅舎は建物を長く作る必要があるので、必然的に同じ形状のものが何度も繰り返されることが多いです。 長野県の安曇野ちひろ美術館 写真は、こちら (美術館ウェブサイト)をご参照ください。 建物の屋根に繰り返しの技法が使われています。 「切妻屋根」の形式をとっていますが、もしこれが一つしかなかったら、無機質な屋根の倉庫のように見えてしまうでしょう。それが5つほど繰り返し同じ形の屋根を連続して繰り返すことによって、全体として見たときに面白みのある風景として出来上がっています。 繰り返し屋根が、周りの景色とよく溶け込んでいるところも美しさのポイントです。 街並みの中での「繰り返し」 商業施設・ミナカ小田原 こちらは最近できた商業施設で、蔵城の建物がいくつも繰り返されており、和風の美しい景色を作り出しています。大きなビルの前面に小さな和風の蔵を繰り返すという点においてもユニークなつくりです。 写真は、こちら(ミナカ小田原ウェブサイト)をご参照ください。 海外の例・イタリア ヴェネツィアのブラーノ島では、建物の外観はよく似たものが連続しているが色がカラフル、という事例もあります。 スタイルが統一されているので色々な色がありカラフルであっても、どことなく統一感のある街並みです。 残念ながらこのタイプは日本では受け入れられないでしょうが、事例としては面白いですね。 海外の例・ギリシャの外観の統一 こちらギリシャのサントリーニ島では、白という「色」で繰り返しがなされています。 同じ色の建物が連続し、その連続により街並みが完成しているので、統一感があって大変美しいですね。 他の国でも、ヨーロッパは屋根瓦の色が同じという例も多々見られます。 こういった色の
2023年 社屋改修工事および夏季休業のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社では誠に勝手ながら、下記の期間中、社屋改修工事のため業務形態を一部変更して営業いたします。 ご来社の際は、弊社までご連絡をいただけますようお願いします。 【社屋改修工事期間】 2023年8月5日(土)~8月20日(日) また、下記の期間中は、夏季休業のため業務をお休みさせていただきます。 休業期間中にいただきましたお問い合わせへの返答は、8月18日(金)以降にさせていただきます。 【夏季休業期間】 2023年8月11日(金)~8月17日(木) お客様にはご不便・ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
美山錦のIWC優勝と日本酒基礎知識
最近、弊社伊藤建築設計事務所が、以前建築で関わらせていただいた会社、株式会社 湯川酒造店さん(長野県)に関する嬉しいニュースが飛び込んできました。 湯川酒造店さんのお酒「十六代九郎右衛門 純米吟醸 美山錦」が、なんと世界的ワインのコンテストIWCの酒部門で優勝されたとのことでした。湯川酒造さんのお酒が海外でも高く評価され、世界で広くご活躍されている様子に、弊社も大変喜ばしく思っています。 今回は「IWCというコンテストはどんなものなのか」「日本酒の基本知識と種類」にも触れながら、今回のニュースについて解説していきたいと思います。 IWCとはどんなコンテストか? 世界最大規模のワイン品評会「IWC」は毎年ロンドンで行われ、”世界でもっとも大きな影響力をもつワインのコンテスト”とも言われています。 そんなIWCに「SAKE部門」が誕生したのは2007年。以来、SAKE部門の受賞酒は国内外で注目され、IWCは日本酒の海外進出における重要なイベントとして、その価値を高めてきました。 審査結果に応じて与えられる評価は「ゴールドメダル」「シルバーメダル」「ブロンズメダル」「大会推奨酒」の4つです。ゴールドメダルを獲得した出品酒の中で特に優れた数点に「トロフィー」の栄誉が与えられ、その「トロフィー」を獲得した中の1点に、SAKE部門の最高賞として「チャンピオン・サケ」の称号が授けられます。 2023年度のIWC、「純米吟醸 美山錦」の受賞結果 2023年度IWCの概要 2023年のコンテストは、7月5日(日本時間)に行われました。 2023年のSAKE部門は9カテゴリーに分けられ、「普通酒」「純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」「本醸造酒」「吟醸酒」「大吟醸酒」「スパークリング」「古酒」の部門に分かれて審査がなされます。審査は銘柄を隠して試飲する、ブラインドテイスティングによって行われたようです。 2023年度IWCのチャンピオン ・サケ「純米吟醸 美山錦」の功績 以下が今回「十六代九郎右衛門 純米吟醸 美山錦」株式会社湯川酒造店(長野県)が獲得した賞です。 ◎純米吟醸酒 部門にてゴールドメダル ◎純米吟醸酒 部門にて純米吟醸トロフィー ◎「チャンピオン・サケ」として最優秀賞受賞 前章のIWCとはどんなコンテ
高輪ゲートウェイ駅と建築
今日は先日初めて行った高輪ゲートウェイ駅についてお話ししたいと思います。 私(今回の筆者)は、幼い頃から山手線に乗る機会が多く身近に感じていたこともあり、山手線に新しい駅ができるとわかった時から、いつか行けるのを楽しみにしていました。 最近コロナ禍も終息し行動がしやすくなったのを機に、今回ようやく新しい駅を訪れることができました。 高輪ゲートウェイ駅の概要 まずは高輪ゲートウェイ駅の概要を簡単にご紹介します。 場所 場所は山手線の田町駅から1.3キロ、品川駅から0.9キロに位置する元車両基地の跡地にあります。 開業 開業は2020年3月14日、49年ぶり30番目の山手線新駅として誕生しました。ただしこれは東京オリンピックに合わせた暫定的な開業だったため、本開業は来年になるそうです。 建物の構造と建築家 建物は地上3階・地下1階建てで1階がホーム2階が改札とコンコースとトイレと店舗、3階も店舗という構造になっています。 駅舎のデザインは隈健吾さんが担当されています。 高輪ゲートウェイ駅の建築に関する発見 開放的な構内 駅でホームに降りた瞬間私が感じたのは明るさと開放感でした。外国の鉄道ターミナル駅、もしくは大きなアーケード街にいる感じを受けました。 これは1階のホームから3階の天井までが吹き抜けていることと屋根に半透明の膜が張られていてそこからやわらかい光が届いているためでした。 折り紙モチーフの屋根 また屋根が不規則に起伏しているのも面白いと思いあとで調べたら折り紙がモチーフになっていると知り納得しました。 屋根の膜の素材は、光は透過させ熱を遮断するものだそうです。 確かに訪れた日は6月のよく晴れた暑い日でしたが、熱気は感じませんでした。 屋根の鉄骨には杉材が挟んでありました。これは膜と合わせて障子をイメージしているそうです。 素材にはガラスと木が多用される 壁面はほぼガラス張りで、一部太陽光発電ガラスが採用されていました。 また改札階の仕切りもガラスが多く使われていて、構内全体がとても開放的である反面、ほこりや汚れが付きやすくもあるので、きれいな状態を保つのは大変そうに感じました。 それから、木が多く使われていることも興味深いと思いました。 主に福島県産の杉が用いられ、内部の壁や天井などに多く使われていました。 &nbs
石川県の建築巡り
先日、休みを利用して久しぶりに2カ所ほど建物を見てきました。 いずれも伊藤建築設計事務所のある長野県ではなく、石川県方面にある建物です。 今日はその際に見てきたものをご紹介します。 金沢21世紀美術館 1カ所目に訪れたのは、金沢21世紀美術館です。 建設されたのが2004年なので、19年ほどたっています。 私の記憶をさかのぼると、2009年ごろに初めて行ったことを覚えています。 その後は伊藤建築設計事務所の会社研修旅行で訪れたりと、何度か足を運んだことがありました。 外観 以下の写真は、2009年の当時撮った写真です。 一方こちらは、今回行った際に撮影した写真です。 外周部が全面ガラス張りになっているせいか、14年経った今でも古くなっている印象はあまり受けませんでした。 今回は、早朝に出発して入場時間より1時間ほど前に到着しました。 こうすることで、屋外のアート作品や、少し早く入ることができる屋内の無料ゾーンを、人が少ないときに見ることができました。 「カラー・アクティヴィティ・ハウス」 屋外には、「カラー・アクティヴィティ・ハウス」があり、子どもたちは立つ位置によってものの見え方が色々と変わるのを楽しんでいました。 「ブルー・プラネット・スカイ」 ここは、屋内の無料ゾーンで私の大好きな場所・タレルの部屋です。 作品名は「ブルー・プラネット・スカイ」といいます。 人気作品「スイミング・プール」 人気作品「スイミング・プール」も見ることができました。 「スイミング・プール」は、以前はコロナの影響で入場制限をおこなっていたり、ウェブ予約を推奨していました。 現在は予約制になっていましたが、特に入場制限等なく鑑賞することができました。(2023年6月現在) まとめ情報 金沢21世紀美術館は、来場者数から見ると国内トップクラスだそうです。 町と美術館をつなぐこのオープンなデザインや、周囲が芝生となってくつろげるスペースがあったり、スイミング・プールの作品もそうですが、様々なワークショップ・プログラムが開催されているキッズスタジオなど子どもが遊べるスペースもあるので、子ども連れの人たちも気軽
住宅、非住宅の価格の推移
今日は 住宅、非住宅についての最近の価格の推移を見て、その後、今後の私の予測をお話していきます。 データは新聞等で独自に調べたものを参照しています。 住宅価格の推移 現状分析 まず住宅について。 現在2023年6月時点で、国内の集成材が2023年4月時点に比べ1割ほど安くなっています。 (※集成材とは、複数の板を結合させた人工の木材のことです。) 2021年から、アメリカでの需要の高まりやコロナ禍のバランス崩壊などが原因でウッド ショックが始まり、集成材の値段も大幅に上昇しました。そして2022年の1月にはウクライナ戦争が始まり、値段は上昇したまま横ばいとなります。 この時点で、日本の住宅の着工数自体は減っていなかったのですが、商社が急いで集成材の原材料(ラミナ)を買い漁ったという背景があります。 この段階では特にカナダ、オーストラリア産のものの買い占めが起こりました。 価格に関してはこのまましばらく横ばいだったものの、2022年7月くらいから、また状況が変わり始めます。 今度は価格が異常な下がり方をし、1ヶ月にだいたい10%近くも下落し続けたのです。 これは慌てて入れた材料を放出したために、集成材の価格が一気に下がったという状態です。 製造コスト、人件費の上昇などがありましたが、それがあったとしても実際の集成材自体は安くなってきているという現状があります。 なお、国産材については、若干の下がりはあるのですが、これは集成材ほどの減少はないという状態です。 今後の推移予測 この記事の筆者の今後の予測ですが、ヨーロッパの方面から仕入れてる集成材原材料(ラミナ)の値段がまた最近上がり始めた現状を見ると、今後また集成材の価格が上昇し始めるのではないかと考えています。 非住宅価格の推移 現状分析 次に非住宅について。 2023年2月から3月頃、電炉大手の東京製鉄で、鋼材価格の引き上げが2%ほどありました。 そして現状2023年5月から6月は、価格を据え置き、つまりそのまま変化はさせないという状態になっています。 鋼材関係の最近の価格変動からの据え置きの裏には、中国の影響があり、中国からの安価な鋼材の流入が原因と言われています。 中国の経済状況、特に不動産関係について触れておくと、今中国国内での需要が減少しており、中国内で消費できない分が日本にも
アーツアンドクラフツ運動と民芸運動
こんにちは。今回の記事は、前々回のブログ記事「美術館企画展レポートとウィリアム・モリスの魅力」の続編です。 前々回の記事に影響を受けて、私(別のブログ担当者です)も美術館に足を運びましたので、そこで考えたことを記載していきます。 ※前回のブログをまだ読んでいない方はこちらから この記事では、ウィリアム・モリスが提唱した「アーツ・アンド・クラフト運動」と、大正から昭和初期に活躍した思想家・柳宗悦によって提唱された「民芸運動」の比較考察を行なっていきます。 二つの理論の違いを、わかりやすい言葉で明らかにしていきたいと思います。 「アーツ・アンド・クラフツ運動」とは何か アーツ・アンド・クラフツ運動とは、簡単にまとめるならば、 ウィリアムモリスのよって先導され、イギリスの産業革命による工業化によって失われた手工芸の復興を目指す民芸運動といえるでしょう。 もう少し噛み砕くと、職人による製作活動と労働の在り方についての問題提唱と理想の提示、ということが言えます。 ではここで、モリスの著書『民衆の芸術』の一文をご紹介します。 私の理解する真の芸術とは、人間が労働に対する喜びを表現することである。その幸福を表現しなくては、人間は労働において幸福であるとは言えないと思う。特に自分の得意とする仕事をしているときには、この感が甚だしい。このことは自然の最も親切な贈物である。 これは、あくまでこの記事の筆者である私の解釈ですが、 モリスは「労働と芸術は決して切り離されることのない隣り合ったものだ」と考えていたのでしょう。 労働があるのならばそこには自然と芸術が生まれるべきであり、それは自然からの親切な贈物だと表現しています。 「アーツ・アンド・クラフツ運動」は、 便利が強調された産業革命において、労働から生まれるべき芸術が生まれず、生活の豊かさが廃れていってしまうことを危惧して始まった運動であったとも言えます。 「民芸運動」とは何か それでは「民芸運動」とは何か見ていきましょう。 「民芸運動」とは、思想家の柳 宗悦 (やなぎ むねよし、名前はしばしば「そうえつ」とも読まれ、欧文においても「Soetsu」と表記される) によって先導され、日本で起こった「日常の暮らしに宿る美しさを追究」する運動です。 彼は、新しい機械や技術で作られた
耐震改修時の問題
今回は、耐震改修における工事中の問題、 特に居住者目線での問題について、実際の現場ではどんな問題が起こりうるのかをシェアしていきます。 これまで伊藤建築設計事務所で請負った耐震改修の一例 建物内部の壁の補強 建物外部への補強材の設置、交換 梁、柱の設置 トグル制震ブレーズの設置 耐震改修のリクエストの傾向 予算的な問題から、「建て替えは難しいので耐震改修を」となるケースが多いです。 耐震改修方法は数多くあるので、発注者様の要望を聞いて選定していきますが、 室内を狭くしたくない 外部の意匠を損ねたくない 居ながら改修を行いたい など、さまざまなタイプのリクエストがあります。 その中でも、 「(居住者の方が) 建物の中に居ながら、改修作業を行なってほしい。改修作業中も建物の中にいたい」 という希望は、ほとんどの方が持たれます。 やはり工事中に移動する場所を確保するのは大変ですし、仮にそういう場所があったとしても、移動場所の改修費・移転費など多くの費用がプラスアルファでかかってしまうためです。 低騒音工法の実際 先に触れた要望が多いこともあり、全ての耐震改修工法は、 「(居住者の方が)建物の中に居ながら、改修作業ができます」「低騒音工法です」と、うたわれています。 ただ一言に低騒音工法だと言っても、メーカーや監理者レベルでは、居住者目線でのを感じ方をうまくとらえられていないことが多いにあります。 それなりの騒音が出てしまうことは工事開始前に分かっていますので、事前説明をさせていただいていますが、 実際に工事が始まると、予想より酷かったという理由で、施工者である私たちが全ての工法で呼び出され、対応を行うことも起こります。 実際の騒音や振動を確認する際、施工の技術者レベルでは、そこまでの問題ではないと判断されるケースでも、居住者の目線で言えば、1日中その騒音・振動にさらされているわけですから(一方技術者は30分のような短い時間だけその場に行って確認をし、その後帰ってしまうのが普通ですから)、一般的に予想されるより実際はデリケートな問題です。 改修中の騒音問題の解決法 工期に余裕があれば、特に騒音が想定される、はつり・アンカー工事などを就業時間後や休日工事とすることも出来ますが、そうすると今度は周辺住民の迷惑になってしまうなど、検討項
企画展とウィリアム・モリスの魅力
今回の記事では2023年4月15日から6月4日にかけて、長野県・松本市美術館で開催中の企画展「アーツ・アンド・クラフツとデザイン -ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで-」に行ってきたレポートをお伝えします。 なお今回は、書き手である私が特に興味のある「ウィリアム・モリス」に焦点を当てその魅力に迫る形で、企画展示で見てきた内容、モリスの魅力についてご紹介していきます。 松本市美術館の企画展示を見に行ってきました。 今回の企画展は「アーツ・アンド・クラフツとデザイン -ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで-」というタイトルです。 19世紀に活躍したイギリス人芸術家で「モダン・デザインの父」モリスが主張した、生活と芸術の融合、そしてその思想に共鳴したデザイナーや建築家により発展した「アーツアンドクラフツ」をめぐる展示でした。 今回の展示会では、モリスのテキスタルデザインによる版押しの壁紙やカーテン、タペストリーといったファブリックの本物が間近に見られるということで、またとない機会を逃すわけにはいくまいと美術館まで足を運びました。 ウィリアム・モリスという人物 1834年イギリスで生まれたウィリアム・モリス(William Morris)は、若いころに父親を亡くし、苦学の末に大学で建築を学びました。一度は建築事務所で働くものの、その後、絵画に移行し家具の絵付けや内外装を手掛け、友人らとのちのモリス商会を立ち上げています。 産業革命で粗製乱造される工業製品が身近に溢れていくのを憂い、手仕事にこだわったテキスタイルや家具、日用品などを制作し、普及にも努めました。彼のこの動きはのちのアーツ・アンド・クラフツ運動の先駆けでもあります。 この記事の著者である私は、昔からモリスファンで、モリスにえもいわれぬ親近感を抱いています。 ということで、今回美術館では、4部構成の展示のうち、モリスを取り上げた前半部分をメインに見てきました。 モリスの作品 彼の手仕事の中で関心させられるのは、例えば、大ぶりな柄の多色刷りの壁紙でも、ムラや継ぎ目が全く目立たず、仕事ぶりが繊細で正確であるということです。 まさにクラフトマンシップを
電気と建物の基礎知識
今日は、私たちの身近にある、電気と建物の仕組みのお話です。 アースって何? まずは今回の最初のキーワードである「アース」について見ていきましょう。 一般的に「アース」と呼ばれるものは、「接地」のことを指しています。 アース(英語:earth)は言葉の通り地球を表し、地面と接触状態になっていることを意味します。 また、地面(地球、earth)とつながっている装置を意味する場合もあります。 「接地抵抗」は、電気機器の本体と地面の間の抵抗値(電位差)のことを指し、地面へどれくらい電流を流せる状態であるのかという目安のことを指します。 身の回りのアース 20m以上の建物には、避雷設備を設備することになっていますが、これには地面へと異常電流を流す設備が接続されています。 また、電気機器周りや家庭の洗濯機、冷蔵等の水回りにもアース線が設置してありますので、この仕組みは皆さんもすでにご存じかもしれません。 落雷や漏電が発生した場合、身体の安全を守ったり、機器を損傷から守ったりしてくれますので、必要不可欠な設備と言えるでしょう。 アースにまつわる取り決め 以上に例を挙げた電気を地面に流す仕組み「アース」は、電気の基本的な設備であり、重要な設備でもあります。 これに関しては、建築基準法や電気事業法、労働安全衛生法などによって法的な取り決めがされています。 当然、接地抵抗には法律で定められた「規定値」があるわけで、この規定値の範囲であればアースは正常に機能し、安全な状態であると言えます。 逆にこの規定値が取れていないと、電気が正常に流れてくれないことになるため、非常に危険な状態であると言えます。 建築の現場ではどんな問題が起きるのか ここでは以前実際に現場で起こった、接地抵抗に関する課題の例を紹介します。 一般的に山間地帯、川沿いでは、接地抵抗が取れない場合が多いので、十分な事前調査が必要です。 事前の地盤調査の結果は、建物の構造を考える上で必須のものですが、一連の電気関連設備を考える上でも必要なものです。 この案件では、設計の段階から事前に専門業者に依頼して、接地抵抗が取得出来るかどうかの調査を行っていましたが、当初より規定の接地抵抗を取ることが困難であることが分かっていました。 そこで考案した解決法は、裸銅線を約2km地中に
アンボンドPC工法とは?
今回は、建築現場でコンクリートにストレスをかける工法として使用される 「アンボンドPC工法」 についてご紹介します。 これはアンボンド工法とPC工法を組み合わせたもので、建築物の床スラブ部分などに使われます。 【用語の説明】 アンボンド工法とは、建築材料を互いに接着させず、重ね合わせることで構造体を作る工法のことを指します。 一方PC工法は、PC鋼材を緊張し、圧縮力を加えたコンクリートを用いた工法のことを指します。 ※PCはプレストレスト(Prestressed)コンクリート(Concrete)の略称 (日本語で解釈すれば「緊張材によりあらかじめ圧縮応力をあたえられたコンクリート」という意味になります。 ) 橋梁や高速道路をはじめとした高い安全性が求められる公共構造物で使われています。 実際の建築の現場では、これらの異なる工法が組み合わせて使われることがあり、 組み合わせることにより建築物全体の性能を向上させることができます。 【コンクリートの特性とRC (鉄筋コンクリー ト)】 今回ご紹介する工法で用いられている素材のコンクリートには、 「圧縮する力には強いが、引っ張る力には弱い」という特性があります。 上記の弱点を、鉄筋で補った構造が、 RC造 (鉄筋コンクリー ト造)です。 ※RCはReinforced Concreteの略です 鉄筋を入れて補強するので、大きな引っ張る力が加わっても壊れることはありません。 しかしRC鉄筋コンクリー トにも弱点があります。 それは、下の引っ張り部分に関して多少のひび割れは避けられないという点です。 【RC鉄筋コンクリー トの弱点を補うPC工法】 そこで考えられたのが、PC工法です。 ※PCはPrestressed Concreteの略です 内部に入れた緊張材によって、あらかじめ圧縮力をコンクリートに加えることにより、 ひび割れを少なくすることが可能になりました。 【アンボンド・PC工法 施工の様子】 施工は鉄筋の配筋前に行います。 コンクリートが硬化した後に、端部のPC鋼線を専用ジャッキにより緊張します。 引っ張ることによりコンクリート内に反力として圧縮力が働きます。 上の写真にも写っている緊張材(鋼より線)については、 例えば最近の一般的なマンションでは、 緊張材には、PC鋼材を7
凡事徹底について思うこと
今回は 「凡事徹底」について思うこと を書いていきます。 「当たり前のことを当たり前にやる」「毎日のことを当たり前にやる」ということが案外難しいということは、私も長い社会人生活の中で感じていることです。 上記に関係する言葉として、「凡事徹底」という言葉があります。 これは、 「何でもないような当たり前のことを徹底的に行うこと、または当たり前のことを他の追随を許さないほど極める」 という意味です。 自分自身の戒めのためにも書いていますが、能力の高い人、パフォーマンスの高い人というのは総じて凡事徹底がなされているのだそうです。 また、企業として高い品質、高いサービスを提供してる会社ほど、トップから下の方まで凡事徹底がされているということがある本にも書いてありました。 身の回りの整理整頓、挨拶といった基本的な行動はもちろんですが、凡事という言葉の中には、 お客様との約束の期限を守る、つまり時間を守ること やると言ったことをきちんとやる というようなことも含まれているような気がします。 これが徹底されていないと結局お客様に迷惑がかかってしまう、つまり会社の評価も下がってしまうように思います。 【イチロー選手のエピソード】 元野球選手のイチロー選手が、記者からのインタビューで 「バッティングや守備をあそこまでのレベルに極めるために、何かやってきたことはありますか」 と聞かれた際に、 「いや 何も特別なことはやってませんが、高校3年間365日、毎日普通の練習以外に夜の10分間の素振りをやってきました」と答えられたそうです。 365日が3年間、つまり1000日以上 毎日やったということだそうです。 もちろん、元々のセンス、経済的に悪い状況でなかったことなども成功の理由だと思っていますが、凡事徹底が大きな結果に結びついた一例ではないかと思います。 【松下幸之助さんのエピソード】 また、松下電工(現 パナソニック)の創業者の松下幸之助さんに関するこんなエピソードも聞いたことがあります。 松下さんは、お施主さん、協力業者を含め、これから取引の発生しそうな企業については、ご自分で足を運びその会社を見に行ったそうです。 その際「凡事徹底 できてるかどうか」を訪問先で見て、その会社とお付き合いするかどうかを判断してきたそうです。 それが故後でトラブルになってせ
学生時代の卒業課題のお話
今回は、今から38年前、私が学生だった時に 卒業課題で計画した建物「ホテル有栖川」 をご紹介します。 建設予定地を東京有栖川宮記念公園に設定し、毎日忙しい人が自分時間をゆっくり過ごせるホテルを計画しました。 以下はロッドリングとスクリーントーンで苦戦しながら製図をした卒業課題の図面です。 【建設予定地】 東京麻布にある広大な公園、有栖川宮記念公園の一画、緑の林に囲まれ、朝には鳥のさえずりを聞きながら目覚めることが出来る所です。 【外観と階の構成】 アプローチを進むと見えてくる外観はRC造4階建のL型外観、仕上げは50角のタイル貼。 1階玄関へ入るとこじんまりしたフロントがお客様を迎えます。あくまでも個人空間的な広さを意識したインテリアをイメージしました。 階の構成は1階がパーティールームとレストラン、2階から4階がシングルルーム、ダブルルーム、スイートルームです。 【コンセプト:くつろぎ】 部屋のコンセプトは「くつろぎ」です。忙しい人達が、自分時間を作りリラックスしながら、心身ともにリセット出来る部屋を考えて計画しました。 特長は部屋の中にあるお風呂で、寝湯スタイルの浴槽になっています。 寝ながら浅い湯につかるので関節や筋肉への負担も軽く、血液がより末梢の血管まで無理なく行き渡ることができます。 ストレス解消、疲労回復に最適の入浴法です。 当時はそこまで分かっていませんでしたが、かけ流しの温泉で横になって見ればその効果は誰でも感じる事ができます。 【おわりに】 当時はどうしたら寛ぎの時間を過ごせる空間が出来るのか、随分考えた事を思い出します。 あれから38年間、建築の設計に携わってきましたが、「いい建物とは何なのか」は未だに答えが出ないままだし、考えている時の感覚は当時のままのような気がします。 あと何年この仕事を続けることが出来るか分かりませんが、最後まで新鮮な志は貫きたいものです。
イオンモール土岐と建築デザイン
先日岐阜県に行く用事があり、その時の帰り道に「イオンモール土岐」というショッピングモールに立ち寄りました。 見どころがいくつかありましたので、今回は 「イオンモール土岐」で見つけたこと、考えたこと などをシェアしたいと思います。 イオンモール土岐とは? 「イオンモール土岐」は2022年の10月にオープンした比較的新しい施設です。岐阜県の土岐市というところにあり、ここは「陶磁器の生産量が日本一」のまちとして知られています。 ■ モールへのアクセスと周辺情報 モールへのアクセスは東西に走る中央自動車道の土岐インターから車で10分、南北に走る東海環状自動車道の土岐南インターからは車で5分ほどで行くことができ、遠くから来る利用者もアクセスしやすい場所にあります。 モールの周辺には美濃焼ミュージアムや県立の陶芸美術館、また、車で15分ほど行ったところに多治見モザイクタイルミュージアムがあります。 ■ 建物の概要 敷地面積は約203,000㎡。建物の延床面積は約72,000㎡、S造の2階建てです。 敷地面積は全国のイオンモールのなかでもトップクラス、延床面積は中規模クラスのようです。先程紹介したトキニワはモールの東側にあります。 モールの周囲には駐車場が配置され、日帰り温泉や住宅展示場、ゴーカートのサーキット場、ガソリンスタンドなどが併設されています。 デザイン面での特徴 先に述べたように陶磁器が地域にとって身近な存在になっているので、イオンモール土岐も建物の外装や内装に土岐市内で生産されたレンガやタイルを使用しています。 建物正面の外壁部分に施されたタイル張りのアクセントウォールは、森や海を表現したパステルカラーとなっています。緑色のタイル部分を近くで見るとこのようになっており、かなり迫力があります。(画像1 ) 土岐市の特色を反映した外装として、 工事中に発生した掘削土を材料に使用し、地元のタイル工房とのコラボレーションで制作された唯一無二のタイルを使って、 森林に差し込むこもれびを表現しているそうです。 以下の画像は、2階のテラスにあるエントランス前です。 右手にレンガ張りが見えますが、このレンガは店内の柱型の仕上げなど内装にも使われていました。建物の中でもよく見かけたのでおそらく地元産のレンガだと思
スマホ・オーディオブック活用読書術
今回は スマホ・オーディオブック活用術と、試してわかったこと についてです。 スマホ・オーディオブック活用読書術 以前にテレビで、こんな読書術を紹介されている著名人がいらっしゃいました。 移動中等にスマホでオーディオブックを聞いて、気に入ったら本を購入する。 聞く速度も1.5倍速等で聞くとより多くの本が聞ける。 私は活字に他人より触れてきていないので、オーディオブックから始めればいいかなと思い、少し前からこの手法を始めました。 オーディオブックのメリット オーディオブックのメリットには以下が挙げられます。 隙間時間で読書が出来る ながら読書が出来る 読書ジャンルの幅を広げられる 倍速機能で速読が可能 等 オーディオブック取扱いアプリ比較 オーディオブックを取り扱っているアプリをいくつか調べてみました。 オーディブル Amazonのオーディオブックです。単品購入の他、月額の聴き放題もあります。 配信は40万作品以上で、聴き放題も12万作品以上です。 配信数が他より多いです。 オーディオブック オトバンクが運営してます。単品購入のほか聴き放題も出来ます。 聴き放題の配信が1万5千作品以上とオーディブルより少ないですがリーズナブルです。 ヒマラヤ 中国の巨大音声プラットフォームの日本サービスです。聴き放題の配信が1万作品以上とオーディブルより少ないですが料金はリーズナブルです。 私は個人的にAmazonをよく利用しているので、オーディブルにしました。 聞ける本は自己啓発からビジネス、健康から小説等様々な本があります。 おすすめ本の発見 オーディブルを試していく中で、面白い本がありました。 佐久の浅間病院の外科部長の尾形先生の「専門医が教える 肝臓から脂肪を落とす食事術」です。 3人の脂肪肝の患者さんが食生活を通して改善していく本です。 また、本の最後のオーディオブック特典のなかで、尾形先生自身のお話がありました。 以前に外科医にとって重大な片目にメスを入れ、目が見えなくなり不安に陥ったことがあったそうです。 その時にオーディオブックを知り、良く聴くようになり救われたとのこと。 自分が本を出版するときはオーディオブック用に執筆しようと思われたそうです。 &nbs
現行プロジェクトの一部ご紹介
今回は 今動いている現場で感じたこと をご紹介をしたいと思います。 白馬で動いているプロジェクトは冬場の工事ということで、雪のため、工期が当初の予定であった2月から3月に延長されました。 過去に手がけた道の駅に続く同じ道の駅関連ですので、1度監理をしたからスムーズにいくだろうと思っていましたが、やはり現場が変われば、施工者も変わり、考え方等も様々になってきます。意思の疎通等の観点も含め、どのように伝えればお互い気持ちよく仕事ができるか、毎回考えさせられます。 またこの現場で一番考えさせられたことは、やはり現場調査はしっかり行わないと実際に現場へ入って苦労するということでした。 今回は後から分かった排水経路関連の事情があったため、工事の増減の調整が必要となりました。 他の監理業務でもそうですが、増減が必要となれば、協議書を作成しなければならず、プラスアルファの仕事が発生します。もちろん仕事が落ち着いていれば、そういう事に充てる時間は十分とれますが、業務が集中している時期にはいろいろ追われてしまうことになります。 また、道の駅の公衆トイレの改修設計で感じたことは、「時代に沿った公衆便所となってきている」ということです。 他の現場でもそうでしたが、衛生器具の部品が膨大な量あります。 今回器具の搬入立会いをしましたが、ある程度小規模な公衆便所であっても大型トラック2台分の段ボール箱が搬入されました。 過去の似たような案件の搬入関係者の話では、 「色々なものがあると把握するのも大変ですし、想像以上にものすごい人工がかかる」とのことでした。 やはり機能や快適さを求めれば業務もそれなりになるのだと、現場監理を通して改めて実感している次第です。 本プロジェクトはまもなく終盤を迎えます。 引き続きしっかりと取り組んで参ります。
トルコ・シリア地震と建築物への影響
今日は2023年2月6日に発生した トルコ・シリア地震と建築物への影響 についてです。 トルコ・シリア地震の実体 日本時間午前10時過ぎに発生したトルコ・シリア地震の規模は、マグニチュード7.8。 そのエネルギーは、2016年の熊本地震の16倍、 阪神・淡路大震災を引き起こした地震の22 倍にのぼり、「世界最大規模の内陸地震」 と言われています。 地表の断層のずれ幅も大きく、 国土地理院が、 宇宙航空研究開発機構(JAXA ジャクサ)の地球観測衛星「だいち2 号」の観測データをもとに分析したところ、 地震による地殻変動はおよそ400キロに及び、阪神大震災の約4倍にあたり、2016年の熊本地震の10倍近く、最大約4メートルの横ずれが生じています。 米地質調査所によると、 最初の地震の規模はマグニチュード7.8、その約9時間後に7.5の余震が起きました。 日本の気象庁の震度に換算すると、 一部で最大の震度7相当の強い揺れが起きていたといいます。 2023年2月23日現在、 トルコ・シリア両国の死者数は計50,000人以上になりました。 世界保健機関(WHO) による推計では最大2,300万人が被災したと見られています。 被災地で避難生活を送る人は100万人以上とみられ、テント30万張りが設置されたほか、仮設住宅 10万戸も設けられるといいます。 建物の倒壊状況とトルコの耐震基準 この地震では、多くの建物が倒壊しました。 その中には、耐震性能をうたう比較的新しいものも含まれていました。 真新しいマンションが崩れた様子に、トルコ国内では怒りの声が上がっています。 全壊した建物の中には、新築の集合住宅も含まれているため、建物の建築基準について喫緊の深刻な懸念が上がっています。 そもそも、今のトルコの建築工法なら、今回のような揺れの強さに建物は耐えられるはずでした。 そして、過去の震災の経験から、トルコでは地震に備えた耐震基準が徹底されているはずでした。 (1999年に北西部イズミットで起きた地震では、1万7000人が死亡しています。 ) トルコでは2018年に発生した災害や、これまでの被災経験から、より厳しい安全基準が導入され、建築規制が強化されてきました。東京大学地震研究所の楠教授によれば[※1]、最新のトルコの耐震基準は日本と変わらない水準だということ
土地の農地転用と農振除外
本日は、 土地の農転農振(農地転用と農振除外) のお話です。 本件は建築設計事務所の仕事なのかという見方もありますが、建物を建てられるようにするには必要です。 よって、農地転用と農振除外という申請が発生することはしばしあります。 農地転用とは? 農転(農地転用)というのは、田んぼ畑等を、宅地・雑種地に変える場合、そこを農地でなくするための申請のことです。 これは市町村の農政課に提出をします。 地区によって異なりますが、だいたい毎月受付をしていただけます。その月の10日ぐらいから15日ぐらいまでに提出をして申請が降りれば、次の月の20日ぐらいには農転がおりるというのがだいたいの目安です。 この手続きに関しては、松本の街中や長野市の街中で、申請を出して一週間ぐらいで許可が降りる場合もあります。 通常はやはり一か月ぐらいはかかるでしょう。 農振除外とは? 元々、農振除外というのは、国が農地を減らさないように定めている場所の、指定を外す手続きです。 一般的にあまりに簡単に農転ができてしまうと、日本の農地がなくなり農作物の自給率が低下してしまうので、それを防ぐためにも国が規制をしている土地なのです。 農振(農振除外)に関しては、地区によりますが、3ヶ月に一回または半年に1回くらいのペースで受付をして頂けます。 事前に農政課に確認をしなければなりませんが、「いつぐらいに農振除外の申請できますか」と聞けば「うちの地域ではこの月に提出してもらいます」といったようにお返事をいただけます。 そして申請月に間に合うよう、準備を行います。 農振除外に関しては、申請を出してから受理まで約半年から1年ほどかかります。 なお、申請した後に、時々農振除外が認められないケースもあります。そういった場合は通常理由などを含めた情報はいただけます。 行政書士との連携 弊社では、農地転用、農振除外いずれに関しても、基本的に行政書士さんに申請を出してもらっています。 申請には図面等も必要になってきますので、弊社で図面等を書き、いつまでに出してくださいと行政書士さんにお願いをします。 その中でも特に、 ・地主さんの許可がいる場合 ・水路がが関わっていて土地改良区さん・水利権者さんの許可を得なければならない場合 上記の場合等には、それ相応の申請もあります。 そういったものを取りまとめ